- ほぼ週刊・本棚から横溝正史 -
 『ナイトランド・クォータリー vol.38』 - 仮面は語る〜真実と偽りの顔のあわいに - アトリエサード/書苑新社, 2025/3/9, 本体:2,073円 | |
内容項目は次の通り。
| |
 本書収録の槇村寛之「方相氏と古代の仮面」や深泰勉「仮面は世界をデザインする」に記されているが、ファントムの仮面が象徴的なアンドリュー・ロイド・ウェバー作のミュージカル「オペラ座の怪人」に、ファントムの仮面の下の醜い素顔にクリスティーヌが恐怖におののくシーンがある。実は、終盤のシーンで「醜さは顔にはないわ けがれは心の中よ」と、クリスティーヌは歌うのだが…。
本書収録の槇村寛之「方相氏と古代の仮面」や深泰勉「仮面は世界をデザインする」に記されているが、ファントムの仮面が象徴的なアンドリュー・ロイド・ウェバー作のミュージカル「オペラ座の怪人」に、ファントムの仮面の下の醜い素顔にクリスティーヌが恐怖におののくシーンがある。実は、終盤のシーンで「醜さは顔にはないわ けがれは心の中よ」と、クリスティーヌは歌うのだが…。本稿では、横溝正史「鬼火」がトマス・ハーディ「グリーブ家のバーバラ」や谷崎潤一郎「春琴抄」「金と銀」との類似、さらには「車井戸はなぜ軋る」「犬神家の一族」へ横溝正史が繰り返して同趣向を使用している旨の指摘がある。 本稿末尾に、 仮面の力を借りることで、人は他者の真の姿を暴き立てるような、暴力的な存在に変化する。惑いや人間的存在から逃れる。哀しみをその底にたたえながら。とあり、まるで、ミュージカル「オペラ座の怪人」そのものであることに思い至る。 本稿にて、参照・紹介された文献ではどのような記述だったのかを、図書館を活用してチェックしてみた。対象文献は、下記の通り本稿で記されている。 横溝が谷崎の強い影響を受けていることは公言しているし[1]、江戸川乱歩が「鬼火」と谷崎「金と銀」の類似を[2」。中島河太郎は「春琴抄」やトマス・ハーディの「グリーブ家のバーバラ」(1890)との類似を指摘している[3]。 本作の舞台を日本に移し、男女を入れ替え、愛する者の美貌の変化に対する反応を突き詰めると「春琴抄」になる。谷崎が「バーバラ」をヒントにしたことは、佐藤春夫の証言が残っている[4]。 [1]「谷崎先生と日本探偵小説」(『谷崎潤一郎全集』月報(1959)、 『横溝正史読本』(小林信彦によるインタビュー、1986) [2]「日本の探偵小説」(『日本探偵小説傑作集』序文、1935) [3]『鬼火』(角川文庫)解説(1975)、『日本推理小説史』第三巻(1996) [4]「最近の谷崎潤一郎を論ず」(1933) ちなみに、谷崎潤一郎訳「グリーブ家のバアバラの話」は、『谷崎潤一郎全集 第12巻 赤い屋根 友田と松永の話 饒舌録』(中央公論新社, 2017/4)を参照した。近隣の図書館に、複数の『谷崎潤一郎全集』が全巻所蔵されていることがわかり、今後のチェックにも活用できそう。谷崎潤一郎訳ではないが、『ハーディ短篇集』(岩波文庫赤240-8, 2000/2)に「グリーブ家のバーバラ」(井出弘之訳)が収録されている。各社の谷崎潤一郎現行文庫には、谷崎潤一郎訳「グリーブ家のバアバラの話」は未収録のようである。 岩波文庫『ハーディ短篇集』の巻末解説(井出弘之)に、谷崎潤一郎訳「グリーブ家のバアバラの話」が「春琴抄」の結実につながる旨、記されている。 わが国では早ばやと谷崎潤一郎がこの作品に惚れ込んで翻訳までしたことは、広く知られている。『春琴抄』(1933)はその折の波紋の結実であるが、しかし、「青い花」や「永遠の偶像」(1922)もハーディの「バーバラ」の影響下に書かれた、というより先に、もともと谷崎にはこの作品を歓迎する素地があったことを見逃してはなるまい。 本稿の参考文献に関する調査結果は、以下の通りだった。 横溝が谷崎の強い影響を受けていることは公言しているし[1]、  [1]「谷崎先生と日本探偵小説」(『谷崎潤一郎全集』月報(1959/5)、『横溝正史読本』(小林信彦によるインタビュー、1986)
[1]「谷崎先生と日本探偵小説」(『谷崎潤一郎全集』月報(1959/5)、『横溝正史読本』(小林信彦によるインタビュー、1986)「谷崎先生と日本探偵小説」は、『探偵小説五十年』(講談社, 1972/9)に収録されており、次の記載がある。 現在探偵作家と呼ばれているひとびとのうち、戦前派に属する作家たちの大部分が、いろいろな意味で谷崎先生の文学の影響を、ひじょうに大きくうけていることは否定できないようだが、とりわけわたしはそれがひどいようである。 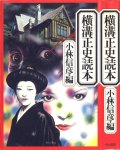 また、『横溝正史読本』「第一部 「新青年」編集長時代から喀血まで」の「谷崎潤一郎と宇野浩二」の項で、横溝正史は次のように語っている。
また、『横溝正史読本』「第一部 「新青年」編集長時代から喀血まで」の「谷崎潤一郎と宇野浩二」の項で、横溝正史は次のように語っている。谷崎さんの影響は、ぼくは子供のときから受けていましたね。だからこの間、誰だかに聞いてみたら、「その作品はあなたの小学校時代ですね」なんていわれたことがあった。 谷崎潤一郎の代表作の多くが発表された、雑誌「中央公論」(兄が購読していた)を読んでいたようである。 江戸川乱歩が「鬼火」と谷崎「金と銀」の類似を[2]。 [2]「日本の探偵小説」( 春秋社『日本探偵小説傑作集』序文、1935/9)  「日本の探偵小説」は、『江戸川乱歩全集 第25巻 鬼の言葉』(光文社文庫, 2005/2)などに収録されており、その「四 作家と作品(その二 ) B 怪奇派 横溝正史」の項に、次の記述がある。
「日本の探偵小説」は、『江戸川乱歩全集 第25巻 鬼の言葉』(光文社文庫, 2005/2)などに収録されており、その「四 作家と作品(その二 ) B 怪奇派 横溝正史」の項に、次の記述がある。彼は谷崎潤一郎の作品を愛することが深く、意識してか無意識にかその着想を借り来ることが屡々であるが、例えば「鬼火」と「金と銀」と、「面影双紙」と「或る少年の怯え」と、「蔵の中」と「恐ろしき戯曲」とには、一部ではあるがその明かな類似を見るのである。  同様の記述が、「一般文壇と探偵小説」(初出:「新小説」1947/1)にあり、こちらは『江戸川乱歩全集 第26巻 幻影城』(光文社文庫, 2003/11)や『開化の殺人 大正文豪ミステリ事始』(中公文庫, 2022/3)などに収録されている。
同様の記述が、「一般文壇と探偵小説」(初出:「新小説」1947/1)にあり、こちらは『江戸川乱歩全集 第26巻 幻影城』(光文社文庫, 2003/11)や『開化の殺人 大正文豪ミステリ事始』(中公文庫, 2022/3)などに収録されている。横溝君なども谷崎文学の心酔者であって、『鬼火』と『金と銀』、『面影双紙』と『或る少年の怯え』、『蔵の中」と『恐ろしき戯曲』等その着想が酷似しているほどである。 江戸川乱歩が記した、谷崎潤一郎「恐ろしき戯曲」は現題「呪はれた戯曲」のことのようである。 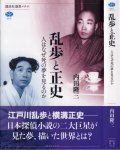 「鬼火」と「金と銀」に関して、内田隆三『乱歩と正史 人はなぜ死の夢を見るのか』(講談社選書メチエ, 2017/7)に、興味深い記述がある。
「鬼火」と「金と銀」に関して、内田隆三『乱歩と正史 人はなぜ死の夢を見るのか』(講談社選書メチエ, 2017/7)に、興味深い記述がある。横溝正史の戦前期の代表作「鬼火」(1935)も、物語の構図という点では、谷崎の「金と銀」(『黒潮』1918/5、その後篇「二人の芸術家の話」は『中央公論』1918/7)を発想の下敷きにしている。正史の「鬼火」は従兄弟どうしで酷似した二人の芸術家の話であり、谷崎の「金と銀」とおなじく、互いに相似形をなす人物をめぐる不安な〈双数〉(double)の現象を扱っている。 中島河太郎は「春琴抄」やトマス・ハーディの「グリーブ家のバーバラ」(1890)との類似を指摘している[3]。 [3]『鬼火』(角川文庫)解説(1975)、『日本推理小説史』第三巻(1996) 角川文庫『鬼火』は、刊行当時リアルタイムでその収録作品と巻末解説(中島河太郎)を読んだ記憶がある。しかしながら、「鬼火」に対する谷崎潤一郎訳「グリーブ家のバーバラの話」や「春琴抄」との類似という、中島河太郎の指摘に注意を払わず忘却の彼方にあったことが悔やまれる。 (江戸川乱歩が「鬼火」と「金と銀」の類似を見ると述べたことに対し) 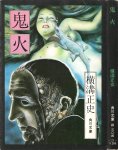 着想に共通性はあっても、潤一郎とはおのずと異なった乾坤が建立されているのだ。『金と銀』は美術学校の同期生の一方が、他の才能に対する嫉妬感を募らせ、たまたま同一の女性をモデルにした展覧会出品を競うことになり、ついに殺害をたくらむ話である。
着想に共通性はあっても、潤一郎とはおのずと異なった乾坤が建立されているのだ。『金と銀』は美術学校の同期生の一方が、他の才能に対する嫉妬感を募らせ、たまたま同一の女性をモデルにした展覧会出品を競うことになり、ついに殺害をたくらむ話である。たしかに似通った点はあるが、それよりトマス・ハーディの『グリーブ家のバーバラの話』や『春琴抄』の一考に価しよう。前者は潤一郎の翻訳紹介したもので、『春琴抄』のヒントになったなったといわれるものだが、(略)  中島河太郎『日本推理小説史 第三巻』(東京創元社,1996)の「第二十七章 横溝正史の転身」にも、詳述されている。
中島河太郎『日本推理小説史 第三巻』(東京創元社,1996)の「第二十七章 横溝正史の転身」にも、詳述されている。それまでの哀愁機智の作風に一転機を画するものであったが、間もなく喀血し、信州で療養生活に入った。大患後、一年半、再起した第一作が十年二−三月の『鬼火』(新青年)である。 諏訪で病を養った作家が、散歩の途次、岬の突端にあるアトリエに踏みこんで、奇怪な画題のカンヴァスに惹かれる。それからその画にまつわる話を、俳諧の宗匠に聞かせて貰うという構成は、いかにも見聞談らしい現実感を具えているが、谷崎の「春琴抄」の手法を想起させる。 谷崎といえば、その翻訳したトマス・ハーディの「グリーブ家のバーバラの話」も、これとゆかりがないわけではない。名門の令嬢バーバラが、ただ美貌というだけで家柄も財産も教養もない男と駆け落したあと、やむなく結婚を承諾した両親は、男に名門の婿に序さわしい教養をつけさせようと旅をさせる。ところが男は劇場の火事に遇って、二目と見られぬ醜い顔になって戻ってきた。彼はそれを恥じて絹のマスクをつけていたが、彼女がどんな顔になっていても驚かぬというので、マスクをとってみせると、あまりのむごさに失神するという場面があるが、これなどは鉄道事故から生命だけはとりとめて帰還した万造がゴムのマスクをつけ、モデル女で同棲しているお銀が求めて仮面をとってもらい、ギャッと叫んだのと相通じている。 本作の舞台を日本に移し、男女を入れ替え、愛する者の美貌の変化に対する反応を突き詰めると「春琴抄」になる。谷崎が「バーバラ」をヒントにしたことは、佐藤春夫の証言が残っている[4]。 [4]「最近の谷崎潤一郎を論ず」(1933) 佐藤春夫「最近の谷崎潤一郎を論ず―春琴抄を中心として」(初出:「文藝春秋」1934/1)は、『現代日本文學大系 30 谷崎潤一郎集1』(筑摩書房, 1969/4)収録分を、図書館で確認できた。さらに、『谷崎潤一郎全集 第12巻』(中央公論新社, 2017/4)解題「グリーブ家のバアバラの話」に、その抜粋がある。 作者の説くところによると、グリーブ家のバアバラの場合――その美貌故に愛していた心からの愛人の美貌が変ってしまったあの場合、日本人ならどうするだろうと仮定を進めてみたり、男と女とを取替えてみたりするうちにあんな風に出来て来たというのがその楽屋ばなしであった。 「春琴抄」といえば、山口百恵・三浦友和を思い出す。この映画を1976年12月公開時リアルタイムで観た世代である。当時、映画鑑賞の前に原作を読んだのだが、佐助が黒目を針で突くシーンにビビってしまった記憶がある(^^;)。 本稿の指摘にあるが、横溝正史が谷崎潤一郎訳「グリーブ家のバアバラの話」を読んだ可能性はあると思われる。原書"Barbara of the House of Grebe'’を、読んでいた可能性もありと考えている。もしくはその両方とも読んでいた可能性もある。それにしても、トマス・ハーディの「グリーブ家のバーバラの話」や谷崎潤一郎「春琴抄」のプロットを、横溝正史は「鬼火」だけでなく「車井戸はなぜ軋る」「犬神家の一族」でも、形を変えながらも繰り返し使用していたことに、驚かされるばかりである。谷崎潤一郎訳「グリーブ家のバアバラの話」を手引きとして、横溝正史「鬼火」を読み進めてみることにしたい。 関連ページ: ・横溝正史関連ニュース&トピックス 谷崎潤一郎『金と銀』(春陽文庫 た24-1, 2025/1/25)刊行! ・ほぼ週刊・本棚から横溝正史 (131) 『鬼の言葉 江戸川乱歩全集 第25巻』光文社文庫, 2005/2 | |
|
さて、次回の「ほぼ週刊・本棚から横溝正史」は…。 キーワードは「???」です。お楽しみに! |
|
横溝正史関連書籍をご存じの方、 耳寄りな情報をお待ちしております。 |
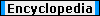 横溝ペディアへ |
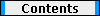 本棚からへ |
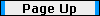 ページの先頭へ |