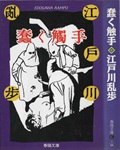 岡戸氏(武平)は博文館にいたことがあり、乱歩名義の『蠢く触手』の代作者でもある。
岡戸氏(武平)は博文館にいたことがあり、乱歩名義の『蠢く触手』の代作者でもある。これは、松村喜雄『乱歩おじさん 江戸川乱歩論』(晶文社,1992/9)「第8章 代作問題について」にある記述である。江戸川乱歩『蠢く触手』は、岡戸武平による代作であることは周知の事実のようである。 『合作探偵小説コレクション5 覆面の佳人/吉祥天女の像』(春陽堂書店, 2024/1)巻末の編者解説(日下三蔵)にも、次の記述がある。 岡戸武平は小酒井不木の助手を経て博文館に入社、横溝正史の下で「文藝倶楽部」の編集に携わる傍ら、自らも探偵小説、時代小説、ノンフィクションを数多く執筆した人物である。「大阪時事新報」に勤めていた頃の乱歩の同僚であり、旧知の仲だったことから、『蠢く触手』の影武者を頼んだのだろう。  また、松村喜雄『乱歩おじさん』の「代作問題について」では、横溝正史が代作した「犯罪を猟る男」「あ・てる・てえる・ふいるむ」「角男」についても触れられている。本書で当方が気になったのは、江戸川乱歩『十字路』は渡辺健治(剣次)氏の代作であり、乱歩の場合、演出が創作と論じられている点である。ただし、春陽文庫『十字路』巻末の落合教幸「『十字路』解説」によれば、「十字路」のプロットは渡辺剣次が協力したもので、それをもとに乱歩が書いたものだった。と記されている。
また、松村喜雄『乱歩おじさん』の「代作問題について」では、横溝正史が代作した「犯罪を猟る男」「あ・てる・てえる・ふいるむ」「角男」についても触れられている。本書で当方が気になったのは、江戸川乱歩『十字路』は渡辺健治(剣次)氏の代作であり、乱歩の場合、演出が創作と論じられている点である。ただし、春陽文庫『十字路』巻末の落合教幸「『十字路』解説」によれば、「十字路」のプロットは渡辺剣次が協力したもので、それをもとに乱歩が書いたものだった。と記されている。 『小説 岡戸武平 乱歩 わが友』(寺田繁, 風媒社, 2025/10/10, 定価 \2,000+税)が刊行された。当方、横溝正史関連の二つのエピソードが記されていることを期待し、本書を読み進めた。確かに、横溝正史に関連する記述をいくつか見つけることができたのだが…。
『小説 岡戸武平 乱歩 わが友』(寺田繁, 風媒社, 2025/10/10, 定価 \2,000+税)が刊行された。当方、横溝正史関連の二つのエピソードが記されていることを期待し、本書を読み進めた。確かに、横溝正史に関連する記述をいくつか見つけることができたのだが…。しばしば乱歩は、鶴舞の不木邸を訪れていた。デビューした翌年には、大阪で知り合った薬剤師の横溝正史と東京へ向かう途次、名古屋駅に降り立つと、その足で鶴舞へ向かったこともある。知らぬは武平ばかりなり。[p.92-93] のちに博文館は長男の新太郎が館主となり、武平が紹介された昭和四年には、新太郎が目を光らせてはいたものの、社長は、その長男の新一だった。講談社と並ぶ出版社であり、編集部長が森下雨村、新人作家では乱歩の他に横溝正史、甲賀三郎、大下宇陀児らが名を連ねていた。[p.127-128] 武平は八月から博文館の社員になった。所属は「文芸倶楽部」の編集部。横溝正史が編集長を勤めていた。若いながら横溝は雨村の覚えめでたく、探偵小説作家としても最近、めきめきと伸してきている。[p.129] 横溝に付いて武平は、次号予告の原案作りから仕事をスタートさせた。[p.130] その頃――横溝正史が編集主任を務める「文芸倶楽部」で原稿取りに明け暮れる最中、博文館を訪ねてきた女がいる。受付から電話で名を聞かされても記憶に無い。会えばわかるだろうと応接室に出向いた途端、吐き気にも似た嫌悪感に襲われた。[p.132-133] 追い返した数か月後の昭和六年、武平は横溝の跡を継いで「文芸倶楽部」の編集主任を命じられた。[p.134-135] 昭和九年は博文館の同僚、横溝正史が大喀血、長野県の上諏訪に転地した年だ。勧めた責任もあって乱歩は、二度、この地を訪れ見舞った。横溝は、諏訪療養中の体験を活かし「鬼火」「犬神家の一族」を発表する。苦難の時期ではあったが災い転じて、といったところ。ともに横溝を代表する、おどろおどろしい作品に仕上がった。[p.176] 「まさしく巨星墜つでんなあ。けどね、周りの誰も、いや本人だって考えもしない死に方でっしゃろ。そやから遺書もおまへんのや」 取り乱しているのか神戸育ちの横溝は、関西弁で喋っているのだが、武平は全く気付かずにいた。[p.317] 横溝に付いて武平は、次号予告の原案作りから仕事をスタートさせた。とあるにもかかわらず、岡戸武平自身が『横溝正史追憶集』収録の「博文館時代の思い出」で、記したエピソード(下記)が、見当たらなかったのは残念である。  私が横溝さんから最初に命じられた仕事は、来月号の予告(二ページ大の引出し)であった。(略)この初仕事を内心得意に思っていると、森下編集局が皮肉な微笑を浮べて編集室へ現れた。この二階には「講談雑誌」と「文芸倶楽部」と「新青年」の三誌の編集部があったが、森下さんはその中央に立つと大きな声で、
私が横溝さんから最初に命じられた仕事は、来月号の予告(二ページ大の引出し)であった。(略)この初仕事を内心得意に思っていると、森下編集局が皮肉な微笑を浮べて編集室へ現れた。この二階には「講談雑誌」と「文芸倶楽部」と「新青年」の三誌の編集部があったが、森下さんはその中央に立つと大きな声で、「"文芸倶楽部"は月に二冊出すつもりらしいね。予告に出しているよ」 私はおどろいて自分の作った予告を見ると、その掲載誌と同じ何月号の大きな活字が飛び込んで来た。 「僕のミスです。スミません」 私は笑う編集局長の前で深々と頭を下げた。冷汗一斗のおもいであった。その時主任の横溝三はまだ出社前で、後刻顔を合せるとこのミスをしたことを報告したら、笑って何も云わなかった。 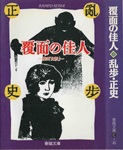 もう一つ。当方の個人的な想いだが、肝心な「覆面の佳人」の横溝正史単独執筆に関する、岡戸武平の証言に関する記述を、同書についぞ見つけることができなかった。岡戸武平といえば、江戸川乱歩・横溝正史『覆面の佳人 或は女妖』なる作品を、横溝正史の単独執筆と証言した人物である。
もう一つ。当方の個人的な想いだが、肝心な「覆面の佳人」の横溝正史単独執筆に関する、岡戸武平の証言に関する記述を、同書についぞ見つけることができなかった。岡戸武平といえば、江戸川乱歩・横溝正史『覆面の佳人 或は女妖』なる作品を、横溝正史の単独執筆と証言した人物である。江戸川乱歩の代作問題は、横溝正史のほかにも数多くあるようで、それらは松村喜雄『乱歩おじさん』(晶文社, 1992/9)の、「第八章 代作問題について」が詳しい。前記三作の他に、横溝正史関連では、1997/10に春陽文庫で初書籍化された新聞連載長編「覆面の佳人或は女妖」について、「直接執筆したのは、やはり横溝氏だろう」との推論の展開は、書誌調査の観点から興味深い論考である。こちらは乱歩との共作名義だが、博文館編集者だった岡戸武平の証言から、実際は横溝正史の単独執筆だったことが、明かされている。その証言は、岡戸武平が「博文館の侍たち・3 昔の文士の生活」(「幻影城」1976/9)で記している。 「酒屋の借金取りだ」 とひとり言のようにいって、また原稿を書き始めた。 その原稿は北海道の地方紙に連載を始めた江戸川乱歩と共作のかたちで発表されたものである。池内氏の地方紙相手の“小説販売”の手によるもので、共作の形となったのは、横溝氏一本では弱いと見られたからであろう。今思うと嘘のような話であるが(この酒屋の話にしても)横溝さんにもこういう時代があった。 『覆面の佳人 或は女妖』文庫巻末「講説」(山前譲)でも引用されており、これを受けて、山前譲は次の通り考察している。 この時、横溝正史が書いていた作品が「覆面の佳人」だったのは間違いない。 この岡戸武平の回顧によれば、「覆面の佳人」は横溝正史の単独執筆となる。したがって本作もまた「犯罪を猟る男」「あ・てる・てえる・ふいるむ」「角男」と同様に、横溝正史による江戸川乱歩作品の代作の一つと見做すこともできる。連名で発表となった事情もおそらく岡戸武平が推測したとおりに違いない。  『合作探偵小説コレクション5 覆面の佳人/吉祥天女の像』(春陽堂書店, 2024/1)巻末の編者解説(日下三蔵)でも同様に、の岡戸武平「博文館の侍たち・3 昔の文士の生活」(「幻影城」1976/9)を引用している。さらに、
『合作探偵小説コレクション5 覆面の佳人/吉祥天女の像』(春陽堂書店, 2024/1)巻末の編者解説(日下三蔵)でも同様に、の岡戸武平「博文館の侍たち・3 昔の文士の生活」(「幻影城」1976/9)を引用している。さらに、『覆面の佳人』は完全なオリジナル作品ではなく、アメリカの女性ミステリ作家A.K.グリーン(Anna Katharine Green 1846-1935)の作品を元にした翻案である。 と論じている。ただ、『覆面の佳人』がグリーンのどの長篇を下敷きにしているかは、いまだに判明していないとも記されており、将来の研究が待たれる。  岡戸武平には、『小説 松江の小泉八雲』(初版:大日本雄弁会講談社,1943, 書影は恒文社1995/12復刊)なる著書がある。NHK朝ドラ(連続テレビ小説)2025年度下期『ばけばけ』の予習に読ませていただいた。本書巻末解説で紹介された、『出雲に於ける小泉八雲』(根岸磐井, 八雲会, 1931)と『へるん先生生活記 』(梶谷泰之, 恒文社, 1998)も、合わせて読み進めている次第。
岡戸武平には、『小説 松江の小泉八雲』(初版:大日本雄弁会講談社,1943, 書影は恒文社1995/12復刊)なる著書がある。NHK朝ドラ(連続テレビ小説)2025年度下期『ばけばけ』の予習に読ませていただいた。本書巻末解説で紹介された、『出雲に於ける小泉八雲』(根岸磐井, 八雲会, 1931)と『へるん先生生活記 』(梶谷泰之, 恒文社, 1998)も、合わせて読み進めている次第。 |
|
関連ページ: ・考古学事始め (32) 代作ざんげと作者返上 ・横溝正史シソーラス(パイロット版) - 温故知新編 - (1-12) ○江戸川乱歩の代作までした横溝正史 |
| 横溝正史に関する情報をご存知の方、 ぜひお知らせください。 |
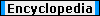 横溝ペディアへ |
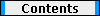 WANTEDへ |
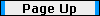 ページの先頭へ |