 『横溝正史に捧ぐ新世紀からの手紙』(角川書店,2002/5)収録の、森村誠一・綾辻行人の対談「横溝作品は知的レジャーランド」で、森村誠一は次のように語っている。
『横溝正史に捧ぐ新世紀からの手紙』(角川書店,2002/5)収録の、森村誠一・綾辻行人の対談「横溝作品は知的レジャーランド」で、森村誠一は次のように語っている。p.34 森村 本格というのは推理小説の原点だと思うんです。本格という言葉に反溌を示す推理作家もいますけれど、やっばり本格は楷書であって、原点だと思います。そして、本格を支えるものは私は遊び心だと思うんです。横溝正史作品はその遊び心が実に横溢してるんですね。本当に全編これ遊び心といってもいいくらい、作品世界に溢れてる。だから、横溝正史の世界というのは、一種の質の高いレジャーランドだと思うんです。知的レジャーランド。その知的レジャーランドが、ここのところ忘れられている。せっかくこれだけの知的レジャーランドがあるんだから、ここでもう一回開館して、できるだけたくさんの読者を招き入れたい。  実は森村誠一は、上記の24年前の横溝正史との対談(「ただいま服役中」<ギルティ対談> 司会構成・山村正夫,vs.森村誠一,『野性時代』1978/6)でも、横溝正史作品をレジャーランドという言葉を使って、評している。
実は森村誠一は、上記の24年前の横溝正史との対談(「ただいま服役中」<ギルティ対談> 司会構成・山村正夫,vs.森村誠一,『野性時代』1978/6)でも、横溝正史作品をレジャーランドという言葉を使って、評している。森村 (略)社会派の出現で、リアリティーがうるさく言われるようになってから、僕が感じ出したのは、推理小説という土俵を自ら取っ払ってしまったのではないかという疑問なんですよ。相撲は本来、土俵の中で取るべきなのに、その土俵を取っ払って柔道やレスリングをやっているような感じを、この頃強く受けるんですね。リアリティーはむろん重要なことですが、それはあくまで推理の土俵の中におけるリアリティーであって、土俵を取っ払ったら、推理小説の生命や存在価値がなくなってしまうんじゃありませんか。 横溝 僕のような型の作家には、自分だけの土俵しかないからね。そこからはみ出そうとは思わないからな。 ―― 言い方を変えれば、お二人ともエンターテインメントに徹した推理小説を書いていらっしゃるわけですよね。 横溝 読者に対するサービス精神は旺盛だよ。それは森村君も同じことじゃないの? 森村 同じですね。そいうった点でも共通性がありますよ。 横溝 それと、話の持っていき方、語り口っていうのかな。そういった工夫を凝らすんじゃないの、二人とも。自分のことを言うのは気がひけるけどね。森村君は抜群にうまいよ。ストーリー・テラーなんだな。あんたは……。 森村 こんな形容をしては失礼かもしれませんけど、僕は横溝先生の作品の面白さは、現代のメルヘンだと思うんですよ。たとえば「八つ墓村」にしても「獄門島」にしても、現実にはあり得ない世界でしょう。そこに横溝推理という楼閣を構築している。ところが、その楼閣に遊びに来て、これは現代にはあり得ないものじゃないかという者がいたら、それはそういった場所へ、遊びに来る資格のない読者ですよ。レジャーランドに入るにはそこの入場券を買って、そこがレジャーランドだということを納得して、入場するわけですからね。 どんな読み方をしようと、読者の自由に違いはありませんけれども、特定の世界で遊ぶにはその約束事を守って遊ぶ方が、ずっと楽しいんじゃありませんか。推理小説を読むのなら、その約束事をよく知ってほしいと現代の読者には求めたいですね。 「横溝作品は知的レジャーランド」こそ、「探偵小説を「お化屋敷」の掛小屋からリアリズムの外に出したかった」(下記参照)という松本清張の言葉に対する、森村誠一の考えではなかろうか。 | |
| |
 なぜなら、講談社大衆文学館『髑髏検校』(文庫コレクション, 1996/3)収録の森村誠一巻末エッセイ「横溝正史の作品世界」で、横溝正史作品のエンターテインメント性を不死鳥になぞらえ、本格探偵小説への回帰は必然と説き、夢とロマンを求めるものこそ、エンターテインメントの土俵と考えられ得るからなのではなかろうか。
なぜなら、講談社大衆文学館『髑髏検校』(文庫コレクション, 1996/3)収録の森村誠一巻末エッセイ「横溝正史の作品世界」で、横溝正史作品のエンターテインメント性を不死鳥になぞらえ、本格探偵小説への回帰は必然と説き、夢とロマンを求めるものこそ、エンターテインメントの土俵と考えられ得るからなのではなかろうか。非日常の世界に構築された本格探偵小説をリアリティの欠落したお化け屋敷と見る読者は、一般市民が日常の亀裂の中に落ち込んでいくリアリティ満点の社会派推理を好む一方、単調な日常にうんざりした読者は、現実の模写にすぎないような社会派推理に辟易して、夢とロマンの復権を求めた本格探偵小説へ回帰していく。 横溝作品は戦前に黄金時代を築き、戦争と社会派推理に圧迫された後、ふたたびよみがえった。横溝氏亡き後、本格推理小説の若い騎手たちによって、推理小説の回帰性が再証明されつつある。横溝正史氏は推理小説の振幅と回帰性の最初の生き証人と言えよう。 将来、推理小説が方向性を見失って拡散しても、横溝作品の土俗的な怪奇性と幻想的な作品世界は、何度でもよみがえる不死鳥なのである。 | |
 森村誠一『遠い昨日、近い昔』(角川文庫, 2019/2/25)の「V 作家だけの証明書 選考委員へ御礼参り」(p.108-109)に、横溝正史との初対面に関するエピソードが記されていることをご存じだろうか。
森村誠一『遠い昨日、近い昔』(角川文庫, 2019/2/25)の「V 作家だけの証明書 選考委員へ御礼参り」(p.108-109)に、横溝正史との初対面に関するエピソードが記されていることをご存じだろうか。当時、乱歩賞受賞者は選考委員に挨拶に行く慣例があった。五人の選考委員中、横溝正史氏、高木彬光氏、中島河太郎氏、仁木悦子氏の四人からはアポイントメントが取れ、それぞれのご自宅を訪問して歓待された。 横溝正史氏は真夏の訪問予定日、あさから部屋を冷やして待っていてくれたそうである。『獄門島』や『八つ墓村』等のミステリーの名著で知られる大巨匠に面会するとあって、こちこちになっていた私を、全く対等に、十年来の知己のように温かく迎えてくださった。私は横溝氏が天下の巨匠であることを忘れ、いい気になって長居をしてしまった。 ようやく尻を上げかけると、横溝氏が、まだもう少しいいじゃないかと引き止めてくれた。 このエピソードは、1969(昭和44)年に森村誠一『高層の死角』が、江戸川乱歩賞を受賞したときのこと。横溝正史との初対面が、よほど印象に残っているのだろうか。森村誠一は自身のエッセイや対談で、同様のことを度々語っている。  たとえば、2002年の横溝正史生誕百周年記念本として刊行された、『横溝正史に捧ぐ新世紀からの手紙』(角川書店,2002/5)収録の、森村誠一・綾辻行人の対談「横溝作品は知的レジャーランド 」では、件のエピソードを森村誠一は次のよう語っている(p.24)。
たとえば、2002年の横溝正史生誕百周年記念本として刊行された、『横溝正史に捧ぐ新世紀からの手紙』(角川書店,2002/5)収録の、森村誠一・綾辻行人の対談「横溝作品は知的レジャーランド 」では、件のエピソードを森村誠一は次のよう語っている(p.24)。森村 私にとって横溝先生は少年時代から愛読していた作家です。江戸川乱歩、海野十三、南洋一郎……ああいう戦前の作家の一人で巨匠だった。私が横溝先生の謦咳に初めて接したのは江戸川乱歩賞の時です。いまは知りませんけど、当時は受賞作家が選考委員にご挨拶に行く慣例があったんです。成城の横溝先生のお宅を訪れたのは夏の暑い日でした。あさから部屋を冷房して、水ようかんを冷やして待っていてくださった。昨日、新人賞を取ったばっかりの人間を。最恵国待遇なんです。これが最初の出会いでした。 綾辻 1969年、でしたね。『高層の死角』で受賞されたのは。 森村 そうです。お忙しい先生だから30分ぐらいのつもりだったんですけど、引き止められまして、多分二時間以上話し込みました。その時に、横溝先生が私の文章をとても褒めてくれました。ああいう文体は若くないと書けないと。最初は固くてコチコチだったんですけど、気さくな方でした。人のいいおじいさんみたい。そんな初対面でした。  さらに、雑誌『本の旅人』(角川書店,1996/10)「特集 金田一耕助とわたし」の特別寄稿として、エッセイ「横溝正史先生の想い出」で森村誠一が次にように記している(p.14-15)。
さらに、雑誌『本の旅人』(角川書店,1996/10)「特集 金田一耕助とわたし」の特別寄稿として、エッセイ「横溝正史先生の想い出」で森村誠一が次にように記している(p.14-15)。昭和44年、私が江戸川乱歩賞を受賞したとき、横溝正史先生は選考委員の一人であった。当時、乱歩賞受賞者は受賞後、選考委員に挨拶に行く慣例であった。いずれも多忙な先生方で、アポイントメントを取りつけるのに苦労したが、横溝先生は、きみの都合のよいとき、いつでもいらっしゃいと言ってくれた。 夏の暑い一日、成城の横溝家を訪問すると、奥様が庭に面した涼しい部屋に案内してくれた。 「横溝が、あなたがいらっしゃるのを朝から待っていたのよ」 とおっしゃって、よく冷えた水羊羹を出してくださった。 『八つ墓村』や『犬神家の一族』『悪魔が来りて笛を吹く』『獄門島』『本陣殺人事件』などと共に、『人形佐七捕物帳』の愛読者であった私は、その作者であり、乱歩先生と共に伝説的な巨匠である横溝先生に初めて会う緊張で、こちこちになっていた。 間もなく着流しで現れた先生は、あたかも十年来の友人のように気さくに言葉をかけてくれた。私はいつしか先生のペースに引き込まれて、ずいぶん生意気なことを申し上げたようにおもう。 約一時間、話題は弾んで、ようやく私が暇を告げかけると、先生はまだ私を引き止めたそうにしておられた。横溝先生は年齢もキャリアも格もまったくちがう青二才の私を、まったく同格に扱ってくださり、一時間も相手をしてくれたのである。  時代はさかのぼって、『横溝正史に捧ぐ新世紀からの手紙』の約20年前、
『横溝正史追憶集』(水谷準:編著, 1982/12, 私家版)に、森村誠一は追悼文を寄稿しており(p.327-329)、その中で件のエピソードを記している。この追悼文は、森村誠一『たった一人からの発想』(講談社文庫, p.307-309, 1994/2)に、「横溝正史先生追悼」と題して収録されている。
時代はさかのぼって、『横溝正史に捧ぐ新世紀からの手紙』の約20年前、
『横溝正史追憶集』(水谷準:編著, 1982/12, 私家版)に、森村誠一は追悼文を寄稿しており(p.327-329)、その中で件のエピソードを記している。この追悼文は、森村誠一『たった一人からの発想』(講談社文庫, p.307-309, 1994/2)に、「横溝正史先生追悼」と題して収録されている。横溝先生に初めてお目にかかったのは昭和44年7月の中頃だったと記憶している。私が江戸川乱歩賞を受賞して、当時選考委員をしておられた横溝先生にご挨拶するためであった。暑い午後で私は全身汗まみれになって横溝家を訪れた。奥様が自ら玄関に迎えてくださり、「今日は朝からあなたをまちかねていたのですよ」と庭に面した涼しい部屋へ招じ入れてくださった。 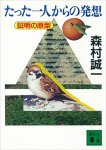 おそらく私の一生で、その謦咳に接することなどあるはずはないとおもっていた推理文壇の巨匠に初めてお目見得するということで緊張しきっていた私を、先生は十年来の旧知の如く親しく迎えてくださった。
おそらく私の一生で、その謦咳に接することなどあるはずはないとおもっていた推理文壇の巨匠に初めてお目見得するということで緊張しきっていた私を、先生は十年来の旧知の如く親しく迎えてくださった。「獄門島」や「八つ墓村」の深潤暗鬱なおどろおどろしい日本の伝承の世界から想像していた先生とはまったく異なる、温容闊達なお人柄にまず驚かされた。 跡で仄聞したところによると、先生の日常生活において、わずかな血を見ても顔色を変えられるほどであるという。その生まの人間像とその想念の中に構築された作品は世界の一体にしてかつミステリアスな距離を感じさせられた。それはそのまま先生の人間と作品領土の広淵なる面積と言うべきであろう。 森村誠一『人間の証明』(旧角川文庫, 新装版とも)巻末解説を、横溝正史が記しているのをご存じだろうか。この解説に次の記述がある。 私はたまたま昭和四十四年頃江戸川乱歩賞の選考委員であり、『高層の死角』を 無条件で推挽した一人だったので、とくに同氏のその後の飛躍成長ぶりには 欣快の上を禁じえない。わが推理文壇は一人の大物を発掘したのである。 『江戸川乱歩賞全集7 伯林-一八八八年 高層の死角』(日本推理作家協会編, 講談社文庫, 1999/9)に、横溝正史の選評「「高層の死角」を推す」(日本推理作家協会会報259 1969/7)が収録されているのだが、森村誠一「高層の死角」のところが欠落しているのが残念。森村誠一「高層の死角」部分は次のように記されていた。 今度の候補作五篇のうち、私の手許へは、「明かりのない部屋」「鮮血のパプテスマ」「虚妄の残影」「高層の死角」「天使が消えてゆく」の順序でまわってきた。(略) つぎにまわってきた、「高層の死角」を読んだとき、私はただちにこれに決めてしまった。推理小説のつねとして、いろいろ無理もあり、説明不足の部分もなきにしもあらずだが、今度の候補作品のなかでは圧倒的に優れていると思った。読みおわったあと、今日の立身出世主義の権化のような犯人像が、かなりハッキリ印象づけられるのもよかった。だいたいこれに決めた。 「高層の死角」の江戸川乱歩賞受賞の際、森村誠一が横溝正史宅に初来訪時、横溝正史は森村誠一をすでに対等の作家として応対している。この横溝正史と森村誠一の関係を周知する必要があるのではと、考える次第。 2022年は、横溝正史生誕120年。本稿で紹介させていただいた、横溝正史と森村誠一との対談、「<ギルティ対談>ただいま服役中」(野性時代1978/6)を歳月の闇に埋もれる前に横溝正史関連の刊本に収録し、後世に残せないものだろうか。 関連ページ: 横溝正史アーカイブス (137):角川文庫『新装版 人間の証明』の文庫解説を読もう! |
| 横溝正史に関する情報をご存知の方、 ぜひお知らせください。 |
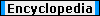 横溝ペディアへ |
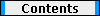 考古学事始めへ |
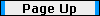 ページの先頭へ |