|
横溝正史エンサイクロペディアを閲覧いただき、誠にありがとうございます。 2016年6月13日、横溝正史クロニクル開設から数えて18周年を迎え、年1シリーズ第18弾!をお届けできる運びとなりました。今年は間に合いました(^^;)。 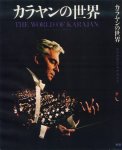 横溝正史のエッセイ「カラヤン知らず」(学習研究社『カラヤンの世界』,1977)掲載)に、次の一節がある。
横溝正史のエッセイ「カラヤン知らず」(学習研究社『カラヤンの世界』,1977)掲載)に、次の一節がある。そういえば、昭和12、13年頃だったろうか。上諏訪の活動写真館に「オーケストラの少女」がかかった。小学低学年だった息子の手を引いて見に行き、銀髪のストコフスキーと可憐な少女歌手ディアナ・ダービンに魅せられた覚えがある。この映画は最近も時折テレビで放映され、先日も懐かしく再見した。あのストコフスキーも、90歳を過ぎたという。まだ現役で活躍しているときいて驚いたが、うたた歳月の流れを感じざるを得ない。 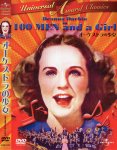 横溝正史が、息子・横溝亮一と連れだって観に行った映画『オーケストラの少女』は、DVD化されており、今日では容易に視聴が可能である。最近になってようやく、この映画をDVDで視聴することが叶いました。横溝正史が信州・上諏訪療養時代に聴いていたと記している、ストコフスキーとフィラデルフィアの「ハンガリアン・ラプソディー」の、ストコフスキー本人が指揮者として出演しています。しかも劇中でも、リスト「ハンガリー狂詩曲」を指揮しています。私にとって、ストコフスキー指揮・フィラデルフィア管弦楽団といえば、ディズニー映画『ファンタジア』なのですが…(^^;)。このエッセイに巡り合えたお蔭で、映画『オーケストラの少女』を視聴できたわけで、時を超えて横溝正史に感謝したいと思っています。
横溝正史が、息子・横溝亮一と連れだって観に行った映画『オーケストラの少女』は、DVD化されており、今日では容易に視聴が可能である。最近になってようやく、この映画をDVDで視聴することが叶いました。横溝正史が信州・上諏訪療養時代に聴いていたと記している、ストコフスキーとフィラデルフィアの「ハンガリアン・ラプソディー」の、ストコフスキー本人が指揮者として出演しています。しかも劇中でも、リスト「ハンガリー狂詩曲」を指揮しています。私にとって、ストコフスキー指揮・フィラデルフィア管弦楽団といえば、ディズニー映画『ファンタジア』なのですが…(^^;)。このエッセイに巡り合えたお蔭で、映画『オーケストラの少女』を視聴できたわけで、時を超えて横溝正史に感謝したいと思っています。横溝正史には、クラシック音楽と関連のある長編『蝶々殺人事件』『悪魔が来りて笛を吹く』『仮面舞踏会』などがあり、これらからもクラシック音楽好きの一端を窺い知ることができる。最近読み直していて見つけたのだが、映画「オーケストラの少女」のストコフスキーは、『蝶々殺人事件』(角川文庫緑304-9, p.35)でしっかり使われていたのには驚かされた。読み飛ばしていたとは、恥ずかしい限りである(^^;)。 コンダクターの牧野謙三はなんだろう。オーケストラ・ボックスの中から飛び出して来て、両手をまえに突き出したまま、茫然として突っ立っていやがったが……あっ、そうだ、思い出したぞ、あれは確かに映画「オーケストラの少女」のストコフスキーだ。うふふふ、奴さん、妙なところでストコフスキーを気取たものだて。 このエッセイの続きの一節に、次のように記されています。 数百枚もたまった当時のSPレコードは戦時の疎開、東京への転居などのゴタゴタにも、失われもせずにきたが、ステレオ時代となってはかけることも出来ず、あたら物置に眠っている。 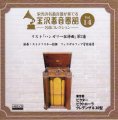 数百枚もたまった当時のSPレコードが、どのようなラインナップだったのでしょうか。横溝正史や横溝亮一は、そのほんの一端しか記しておらず、クラシック音楽のファンのみならず、気になるところです。今となってはもはや知る由もなく、個人的にも非常に残念に思っています。しかしながら、横溝正史が愛でたこれらのクラシック音楽は、当時の録音のものがCD化されており、いくつかは入手できました。1930年代の録音ですが、それぞれ素晴らしい演奏だと思います。これらのクラシック音楽が、横溝正史の執筆活動にどう影響を与えたかを知る意味でも、数百枚もたまった当時のSPレコードのラインナップ調査が進み、当時の音源を集めて、「横溝正史が愛でたクラシック音楽」と題したCD集を、どこか発売してくれないものだろうか。私は間違いなく購入するのですが、聴いてみたいと思うのは、私だけではないだろうと思う次第。
数百枚もたまった当時のSPレコードが、どのようなラインナップだったのでしょうか。横溝正史や横溝亮一は、そのほんの一端しか記しておらず、クラシック音楽のファンのみならず、気になるところです。今となってはもはや知る由もなく、個人的にも非常に残念に思っています。しかしながら、横溝正史が愛でたこれらのクラシック音楽は、当時の録音のものがCD化されており、いくつかは入手できました。1930年代の録音ですが、それぞれ素晴らしい演奏だと思います。これらのクラシック音楽が、横溝正史の執筆活動にどう影響を与えたかを知る意味でも、数百枚もたまった当時のSPレコードのラインナップ調査が進み、当時の音源を集めて、「横溝正史が愛でたクラシック音楽」と題したCD集を、どこか発売してくれないものだろうか。私は間違いなく購入するのですが、聴いてみたいと思うのは、私だけではないだろうと思う次第。「歌手が来りて推理小説を語る 大橋国一 声楽家」音楽の友S49(1974)/1 『新版 横溝正史全集18 探偵小説昔話』(講談社, 1975)収録 で、横溝正史がかけたという、ベートーヴェン交響曲第6番「田園」の第4楽章「嵐」は、横溝正史が聞いていたと記している、ワルター指揮/ウィーン・フィル1936年録音のものを、現在CDで入手可能である。  亮一(略)戦争中、昭和二十年の東京の空襲の最中、頭の上で空中戦やってすごい音しているときに、親父が防空壕からヒョコヒョコ出ていって、いきなりものすごくでかい音で電蓄をかけ始めたんだよ。当時の電蓄だよな。ベートーベンの「田園」の嵐のところね。こっちのほうがよっぽどでかい音するぞって親父言ったのを覚えているんだ。中学の二年くらいだな。
亮一(略)戦争中、昭和二十年の東京の空襲の最中、頭の上で空中戦やってすごい音しているときに、親父が防空壕からヒョコヒョコ出ていって、いきなりものすごくでかい音で電蓄をかけ始めたんだよ。当時の電蓄だよな。ベートーベンの「田園」の嵐のところね。こっちのほうがよっぽどでかい音するぞって親父言ったのを覚えているんだ。中学の二年くらいだな。横溝 あのとき家の真上で艦載機と日本の戦闘機が空中戦やって、子供が脅えちゃいけないと思って「田園」の一番音の大きいとこかけちゃったよ。 今までなぜか当サイトで紹介していなかったのですが、『さよならドビュッシー』『おやすみラフマニノフ』『いつまでもショパン』『どこかでベートーヴェン』の岬洋介シリーズで、クラシック音楽を融合したミステリ作品を執筆されている中山七里が、楽天ブックスサイトの『さよならドビュッシー』著者インタビューで、次のように語っている。やや強引なクラシック音楽つながりですが…(^^;)。 −−この作品は“岬洋介シリーズ”の第一作ですが、司法試験にトップで合格したピアニストという、ユニークな探偵役・岬のキャラクターはどこから生まれたのでしょうか。 中山さん 僕は横溝正史さんの小説に出てくる、金田一耕助のキャラクターが好きなんですね。そこで、ピアノを弾くイケメンの金田一にしようと。ただ岬は探偵役ではありますが、事件の解決よりもみんなの幸せを願う、狂言まわしのような存在なんですね。彼のような人物がいれば、ヒロインがどんな悲劇や困難に見舞われても暗い話にはならないだろうし。大映ドラマを踏襲するなら、コーチ役が必要だということで生まれたのが岬洋介ですね。 『さよならドビュッシー』を読んだ時、探偵役の岬洋介というキャラクターに金田一耕助が見え隠れしたように思えたのですが、作者が意図していたということがわかり納得です(^^;)。映画『さよならドビュッシー』で岬洋介役を務めた、ピアニスト・清塚信也のモジャモジャ頭は、金田一耕助の風貌を意識したものだったのでしょうか。 『横溝正史追憶集』(水谷準:編著, 1982/12, 私家版)に寄稿した横溝亮一の文章に、次の一節がある。横溝正史が愛でたクラシック音楽を聴きながら、横溝正史の作品を読み進めるのも、また一興に思う今日このごろ。 最晩年の父は国立医療センターの病室にカセットを持ちこみ、上諏訪時代に親しんだ「美しく青きドナウ」や「ハンガリア狂詩曲」を楽しそうに聴いていた。 『横溝正史追憶集』には、軽井沢滞在中、横溝正史が散歩途中に通った喫茶店離山房マダム・槇野あさ子さんの寄稿に、横溝正史とクラシック音楽に関する、アッと驚くような記述がある。何の曲を指揮されたのだろうか、気になっている。 "マダム、今日は交響楽を指揮するんだよ" 私はご冗談だろうと笑っておりましたら、本当に軽井沢プリンスでオーケストラを指揮なさったそうです。 これからも、ゆっくりではありますが着実に、横溝正史の書誌データをもとに、創造しい想像を展開していきたいと考えています。今後とも「横溝正史エンサイクロペディア」をよろしくお願いいたします。 |
|
Jiichi |
|
横溝正史関連の書誌情報について より詳しくご存知の方、ぜひご一報ください。 |
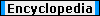 横溝ペディアへ |
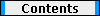 About...へ |
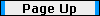 ページの先頭へ |