|
なぜ今まで片岡義男の(書き下ろし)珈琲エッセイ本がなかったのか?と、帯の惹句についつい惹かれて、片岡義男の珈琲エッセイ『珈琲が呼ぶ』(2018/1, 光文社)を読む。読んでいる途中で、ずいぶん前に同氏の紅茶に関するエッセイ文庫を読んだ記憶がよみがえってきた。内容をまるで忘れていたのですが、なぜか矢も盾もたまらず、片岡義男『アール・グレイから始まる日』(1991/5/25, 角川文庫)を古本屋で探しあてた。読み始めてすぐに、横溝正史に関する記述に遭遇しました。虫の知らせだったのでしょうか。その後、『珈琲が呼ぶ』に戻ったのは言うまでもない(^^;)。 片岡義男『アール・グレイから始まる日』に、次の記述がある。 「おいしかった二杯の紅茶」より抜粋  僕がこれまでに日本で飲んだ紅茶のなかで、おいしさをいまでもはっきりと記憶している紅茶は、二杯しかない。一杯は植草甚一さんの自宅で出していただいた紅茶。そしてもう一杯は、横溝正史さんの軽井沢の別荘で出していただいた紅茶だ。日本で飲んだ紅茶のうち、おいしさで記憶している紅茶はこの二杯だけだ。とくりかえして僕は強調しておきたい。
僕がこれまでに日本で飲んだ紅茶のなかで、おいしさをいまでもはっきりと記憶している紅茶は、二杯しかない。一杯は植草甚一さんの自宅で出していただいた紅茶。そしてもう一杯は、横溝正史さんの軽井沢の別荘で出していただいた紅茶だ。日本で飲んだ紅茶のうち、おいしさで記憶している紅茶はこの二杯だけだ。とくりかえして僕は強調しておきたい。横溝さんの別荘を訪ねたときは、FM局の番組に横溝さんのインタヴューが必要だったからだ。インタヴューアーの爆破、関係者数人とともに、ある夏の日の午後、上野から電車に乗って出むいた。よく晴れた夏の日、さわやかな風の吹く林の中にあった静かな別荘に居間で、僕たちは紅茶をごちそうになった。このときの紅茶も、奥さんが入れてくださった。植草さんの場合とおなじく、ごく普通の紅茶なのだが、素晴らしくおいしかった。同行した女性たちもそう言っていた。 植草さんや横溝さんの奥さまが属している世代の人たちが、ほんとに自分のものとして身につけて持っている、ものごとの微妙で適切な案配、判断、加減などの能力が、紅茶のおいしさを作り出していたのではないかと、いま僕は確信を持って思う。そのような本能的と言っていい能力に、年季、つまり雑念のなさが重なり、紅茶は完璧なおいしさとなった。 そして当時の僕は、ありとあらゆる雑用的な仕事が僕をめがけて降ってくる、といった多忙な日々の中にあった。植草さんや横溝さんに会う時間は、多忙さのなかにすこしだけぽっかりと空いた救いの時間であり、その時間のなかで、一杯の紅茶は僕をこの上なく慰めてくれた。どちらのときも、僕は二杯めをお願いした。このことは大変な正解だったのだと、いまでも僕はひそかに自慢に思っている。 このエッセイを読んで、奥さんの入れた紅茶を、「また、紅茶か」といいながらもおいしそうに飲む横溝正史の笑顔が、私の脳裏に鮮やかに蘇ってきた。私にはこのシーンを見た記憶がある。それは、市川崑監督の映画『病院坂の首縊りの家』のラストシーン。片岡義男のエッセイで言及している、横溝正史の奥さんが入れた紅茶は、映画のワンシーンとして、私の脳裏に焼き付いていたようだ。  実は、映画『病院坂の首縊りの家』(1979/ 5)は老推理作家(横溝正史)宅での金田一耕助に紅茶を出すシーンで始まり、老推理作家(横溝正史)が「また紅茶か」というシーンで終わる。『キネマ旬報 No.761』(1979/5下, p.76-100)収録のシナリオには、次のように記されている。
実は、映画『病院坂の首縊りの家』(1979/ 5)は老推理作家(横溝正史)宅での金田一耕助に紅茶を出すシーンで始まり、老推理作家(横溝正史)が「また紅茶か」というシーンで終わる。『キネマ旬報 No.761』(1979/5下, p.76-100)収録のシナリオには、次のように記されている。シーンNo.1 老推理作家が、訪ねて来た金田一耕助を玄関から古めかしい洋風の応接間に招じ入れるところから、この映画は始まる。昭和二十六年の初冬の午后のことである。老推埋作家の住居は、或る都市(県庁所在地)の郊外にある。 老推理作家「まあ上り給え。よく来たね。何年ぷりかなあ」 金田一「ご無沙汰しました」 老推理作家「うん。それで、どこか遠くに旅行するんだって?」 金田一「ええ。また、しばらくお会いできないと思いましたので……」 この時、明るい感じの若い女性か応接間に入ってくる。金田一に会釈すると、テーブルの上に散らかっている新聞や雑誌を手早くかたづけ始める。 老推理作家「(金田一に)遠縁の娘だ。妙ちゃんと言うてな。ときどきぼくの原稿の清書や、うちのばあさんの手伝いをしに来て貰っているんだ。ふだんは大学で薬屋の勉強をしている」 妙ちゃん「(老推理作家を睨んで)薬物学専攻です」 老推理作家「(妙ちゃんに)こちらはぼくの友人の金田一君。探偵さんだ」 金田一と妙ちゃん、お辞儀をかわす。 老推型作家「(妙ちゃんに)この人はね、難しい事件を解決したあと、どこかへ姿をかくすという癖があるんだ」 妙ちゃん「おじさまの書かれた推理小説に、そんな探偵が出てくるのがありましたわ」 老推理作家「そうかね」 妙ちゃん「(金田一に)どちらへ行かれるんですか?」 金田一「はあ。アメリカへでもと……」 老推理作家「え?! アメリカヘ……」 金田一「はあ」 老推理作家「出国手続きが大変らしいじゃないかい」 全田一「はあ」 妙ちゃん「アメリカはストレスとか自閉症とか脳神経関係の薬品は確かに進んでいますわ」 金田一 「は?」 老推理作家「どうしても行くのかね。人間のいるところはどこへ行っても同じだがねえ」 金田一「……」 老推理作家「(奥のほうへ大声で)おーい! 金田一君がみえたんだ。お茶を持っておいで!」 奥のほうから奥さんの声『わかっていますよ。いま支度しています』 シーンNo.2 茶の間で奥さんが紅茶をいれている。 シーンNo.3 応接間。 老推理作家「船で行くつもりかね」 金田一「はあ」 老推理作家「パスポートはもう用意したのかね」 金田一「いえ、これからです」 老推理作家「写真がいるね」 金田一「それもこれからです」 老推理作家「写真だったら、創業明治二十五年という古い写真館を知ってるよ。ここから少し遠いが、行ってみるかね」 金田一「どこでもいいんですが」 老推理作家「しかし、名前を忘れたなあ。行ったのが七、八年も前のことだから」 妙ちゃんがプッと吹き出す。 奥さんが紅茶を持って入って来ながら、「本條写真館のことでしょ。(にこやかに金田一を見て)いらっしゃい」 老推理作家「(奥さんに)おい、金田一さんはアメリカへ行くそうだ」 奥さん「へーえ……外国へ?!」 金田一耕助(石坂浩二)や、妙ちゃん(中井貴恵)との絡みのあるシーンに、ご夫婦で出演。長セリフをそつなくこなす名優といった風格を感じます。そしてラストシーン。 シーンNo.137 老推理作家の応接間。 春が近い昼。 妙ちゃんと黙太郎がいる。傍で煙草をくゆらしている老推理作家。 黙太郎「……金田一さんは、もうアメリカから帰って来ないつもりですかねえ」 妙ちゃん「このお宅に、三ヶ月ほど前に一度、便りがあったきりです」 黙太郎「あの人はぺシミストだからなあ」 妙ちゃん「金田一さんはそういう格好をするのが好きなんじゃないかしら。本当は楽天家だと思うわ」 茶の間では、奥さんが紅茶を入れているらしい。 黙太郎「なにか、仕事がありませんか。なんでもやりますよ」 妙ちゃん「写真館はどうしたの」 黙太郎「ぼくがやめたら、すぐ潰れちゃいましたよ。法眼家もどうなるか……」 老推理作家「あったものは、こわれていく。そのときに、また新しいものが生まれるんだよ……」 完 シナリオでは、老推理作家の上記のセリフで終わっていますが、映画本編ではさらに続きがあり、 奥さんが紅茶を持って来て、「いらっしゃい」 老推理作家「また、紅茶か」 で、映画が締めくくられます。DVDでぜひご確認を!  このラストシーンについては、『横溝正史追憶集』(私家版, 水谷準編,1982/12)収録の「紅茶」で、市川崑自身が次のように語っている。
このラストシーンについては、『横溝正史追憶集』(私家版, 水谷準編,1982/12)収録の「紅茶」で、市川崑自身が次のように語っている。お宅へお邪魔するたびに、奥さんがお茶を運んでくださる。いつも温かい紅茶であった。そのことが心に残っていたので、「病院坂の首縊りの家」のラスト・シーンを、これで締括った。 私としては、この「病院坂の首縊りの家」を金田一シリーズの最後の映画にしようと思っていた。もう飽きたとか、もう面白いストオリーがないというのではなく、私も映画をあと何本つくれるかわからない年齢なので、自由な発想の作品を、自由な作品を、自由な時間で製作したいというのが理由であった。 横溝さんに、金田一と親しい老推理作家(横溝さんのようであり、ようでもなさそうな人物)という役で、奥さんと一緒に出演して貰った。金田一が事件を解決して飄然とアメリカへ渡ってしまったあと、金田一を憧憬している若い男女が老推理作家の応接間を訪れ、三人で金田一のことを懐かしがっている場面。そこへ、奥さんが紅茶を持って入って来る。それを見た老推理作家が「また、紅茶か……」と、ぼそっと言う。その台詞をキッカケにエンド・マークが出る。もちろん、実際には横溝さんが「また、紅茶か」と言われたことはないし、そう思われたこともないだろうし、私も思ったことはない。私は、その何気ない台詞で、老夫婦の爽やかな親愛の日常を暗示してみた。そして、そういう情景が、この映画のラスト・シーンにふさわしいと思ったのである。 横溝正史が紅茶好きだったことは、下記文献からも窺い知ることができる。 「一週間にこれだけ食べました」(週刊読売,1977/9/10, p.111)の一週間の食事表に毎日のように記されており、サントリーの白(ウイスキー)と合わせ、横溝正史の執筆活動になくてはならないものだったことが窺い知ることのできる。 この食事表には記されてはいないが、散歩途中にお気に入りの喫茶店に立ち寄り、コーヒーを飲むのも日課だったようである。 |
| 横溝正史に関する情報をご存知の方、 ぜひお知らせください。 |
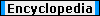 横溝ペディアへ |
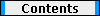 WANTEDへ |
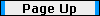 ページの先頭へ |