|
『横溝正史読本』(角川文庫, 2008/9改版復刊)収録「年譜」の昭和昭和七年(1932)の項を見ると、夏、博文館を退社。作家生活に入る。(略)十一月、赤坂の料亭「幸楽」にて激励会「横溝正史君の会」が催される。当時の在京探偵作家のほぼ全員が出席。とある。雑誌編集者を辞し、文筆業一本となった横溝正史は、昭和7年当時の心境を、自作中の登場人物に自分自身を投影し書き残している。それは昭和7年8月刊行の『呪いの塔』で、狂言廻し役を務める由比耕作である(細谷正充による解説, 徳間文庫版『呪いの塔』(2006/11)より)。作中、次のように語られている。 この由井耕作という男は、探偵雑誌の編集をしているばかりでなく、自分でもときどき探偵小説を書いていた。彼はこの両天秤式な生活にひどく不愉快を感じながら、それでいてそのどちらをもよすことができなかった。なぜならば、彼のこの二つの仕事から得る収入は、ほとんど同じくらいであって、そのどちらをよしてもたちまち収入が半分に減るわけだった。生活に対してひどく臆病なこの雑誌記者兼探偵小説家は、長いあいだ、だからどちらともつかぬ生活態度をとってきていた。そしてその過剰な仕事の負担のために、近ごろではだんだん生活に対して無気力になりつつあった。 最近いろんな機会にそれを意識してくると、さすがに臆病なこの男も、急に今までの両棲的な生活が不愉快になってきた。すると、この男のくせで、一時に何もかもさっぱりかたがつけたくなったのであった。この男は今も言ったとおり、大変臆病であるくせに、物事が行きづまりになると、妙に図々しく、肚の据わってくるところがあった。それは度胸というのではなくてたかをくくるのだった。 「なあに、どうにでもなるさ」 それが行きづまったときのこの男のモットーだった。そして、最近とうとうそういう心境にまで行きついていた。 これを裏付けるものとして、「途切れ途切れの記 7 喀血で狼狽のこと」(『探偵小説五十年』講談社, 1977/8)が、上記細谷氏の解説でも挙げられている。この二つを重ね合わせることで、『呪いの塔』の文章は、横溝正史の当時の心情そのものを表しているといっても過言ではない。 昭和七年夏博文館を退いた。 理由は『新青年』『文芸倶楽部』『探偵小説』と歴任しているうちに、私はすっかり倦み疲れてしまったのである。(略)世の中を甘くみる癖がついてしまった私は、『新青年』には水谷準君がいてくれるし、ほかの雑誌編集長にも親しい友人が大勢いるし、それに私はいたって小器用にうまれついているのである。定収入を失っても、なんとか食っていけるだろうくらいにタカをくくっていたのである。作家として立っていこうという決心もなくはなかったが、売文業で食っていけるはずだと思っていた。  江戸川乱歩 『貼雑年譜 江戸川乱歩推理文庫特別補巻』(講談社,1989/7)の昭和八年度の頁を紐解くと、昨年ノ部ニ貼リ忘レタノデコヽニ出ス。という注意書きと合わせ、「展望台」という新聞(?)の切抜き記事「横溝君を世に出す會」に、江戸川乱歩手書きコメントが添えられている。
江戸川乱歩 『貼雑年譜 江戸川乱歩推理文庫特別補巻』(講談社,1989/7)の昭和八年度の頁を紐解くと、昨年ノ部ニ貼リ忘レタノデコヽニ出ス。という注意書きと合わせ、「展望台」という新聞(?)の切抜き記事「横溝君を世に出す會」に、江戸川乱歩手書きコメントが添えられている。横溝正史君の会(昭和七年十一月十二日) 博文館ヲヤメ文筆専業トナル首途ヲ励マス会デアッタ。 記事を読むと、この「横溝君を世に出す會」は随分と大人数の参加者でかつ無礼講だったことが窺える。横溝正史の人望もさることながら、それは取りも直さず、横溝正史に対する参加者の期待の表れだったのではないだろうか。  去る十二日赤坂「幸楽」に開かれた「横溝正史君の会」は森下雨村氏の開会の辞に始まり江戸川氏、辰野氏その他数氏の激励の辞があり当夜は探偵小説家オンパレードの盛況で集まる者六十九人、宴たけなはなる頃津田寓伯は突如素っ裸になり本位田君の歌に合わせてエログロダンスをやり流石の猛者連を驚かした一同横溝君の「万歳」を三唱して散会したのは九時過ぎであった◆正面席の大家連のうち江戸川氏、浜尾氏と光彩陸離たる頭が列ぶ、悪い奴が「をしい事に三光そろはないね」と言つた途端その隣に居た森下氏が頭をあげるとオデコがぴかぴか
去る十二日赤坂「幸楽」に開かれた「横溝正史君の会」は森下雨村氏の開会の辞に始まり江戸川氏、辰野氏その他数氏の激励の辞があり当夜は探偵小説家オンパレードの盛況で集まる者六十九人、宴たけなはなる頃津田寓伯は突如素っ裸になり本位田君の歌に合わせてエログロダンスをやり流石の猛者連を驚かした一同横溝君の「万歳」を三唱して散会したのは九時過ぎであった◆正面席の大家連のうち江戸川氏、浜尾氏と光彩陸離たる頭が列ぶ、悪い奴が「をしい事に三光そろはないね」と言つた途端その隣に居た森下氏が頭をあげるとオデコがぴかぴか
こうして、昭和7年に作家専業となった横溝正史ではあるが、翌年の昭和8年5月7日に大喀血し、長期療養生活に入ることとなるのは、ご存じの通り。 関連ページ:
|
| 横溝正史に関する情報をご存知の方、 ぜひお知らせください。 |
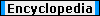 横溝ペディアへ |
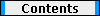 考古学事始めへ |
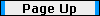 ページの先頭へ |