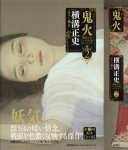 『横溝正史ミステリ短篇コレクション2 鬼火』(日下三蔵編, 柏書房, 2018/2)巻末の編者解説に、「蔵の中」の加筆改稿に関して、次の記述がある。 『横溝正史ミステリ短篇コレクション2 鬼火』(日下三蔵編, 柏書房, 2018/2)巻末の編者解説に、「蔵の中」の加筆改稿に関して、次の記述がある。最後に作品の異同について触れておこう。「蔵の中」には初出から大きく加筆された箇所があるが、初刊の春秋社版での加筆であるため、これを活かした。 「蔵の中」は、雑誌『新青年』1935(昭和10)年8月号(発売は7月初めか?)が初出である。 1935年9月10日刊行の春秋社版『鬼火』に収録された「蔵の中」は、その初刊に当たる。 その際、横溝正史本人による加筆改稿がされていたと、上記の記述は解釈できる。 初出「蔵の中」掲載の最後に、「1935.6.3」と脱稿日(?)が記されています。ということは、横溝正史による加筆は初出掲載の直後に行われて、その初刊の春秋社版『鬼火』(1935/9)に収録されたことになります。加筆改稿版が刊本になったので、今までに刊行された「蔵の中」収録刊本の「蔵の中」は、全て(?)「加筆改稿版」だと考えられる。全ての刊本をチェックするまでもなく(^^;)。我々が現在容易に読むことができる「蔵の中」は、「加筆改稿版」ということになる。そうなると、私のように初出版「蔵の中」を読みたいと考えるのも、自然の摂理とでも言えるのでは…。 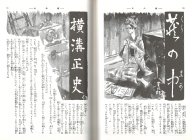 つまり、現在流通している「蔵の中」は1935年の横溝正史による加筆改稿版で、
加筆改稿前の「初出版」の「蔵の中」を読むためには、初出に当たるのが、一番の近道。そう、雑誌『新青年』1935年8月号にである。
あまり知られていない(?)のかもしれませんが、
雑誌『新青年』は全巻復刻版が、本の友社より刊行されています。
こちらは、雑誌掲載そのままの状態で復刻されているので、
初出版「蔵の中」を読むことが可能というわけです。
この復刻版は、公立図書館などに所蔵しているところも多々あるようです。
雑誌『新青年』1935(昭和10)年8月号を探すより容易ではと、個人的には考えています。
つまり、現在流通している「蔵の中」は1935年の横溝正史による加筆改稿版で、
加筆改稿前の「初出版」の「蔵の中」を読むためには、初出に当たるのが、一番の近道。そう、雑誌『新青年』1935年8月号にである。
あまり知られていない(?)のかもしれませんが、
雑誌『新青年』は全巻復刻版が、本の友社より刊行されています。
こちらは、雑誌掲載そのままの状態で復刻されているので、
初出版「蔵の中」を読むことが可能というわけです。
この復刻版は、公立図書館などに所蔵しているところも多々あるようです。
雑誌『新青年』1935(昭和10)年8月号を探すより容易ではと、個人的には考えています。初出版「蔵の中」は、下記の「本の友社復刻版」に収録されています。 「新青年」復刻版 (本の友社, 1992/2) 昭和10年(第16巻) 合本5 第9号(8月号)・第10号(夏期増刊号) 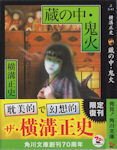 柏書房版刊本の編者解説で、「初出から大きく加筆」と記されている箇所は、
おそらく下記と考えられる。「初出」では、「鏡の中の恍惚」の記述が2行ほどですが、
柏書房版では約2ページ半にわたる加筆改稿になっています。ちなみに、「蔵の中」は
角川文庫版『蔵の中・鬼火』(2018/7改版初版)という、現行本で読むことが可能となっており、そちらでは約3ページにわたる加筆改稿の分量に相当する。
柏書房版刊本の編者解説で、「初出から大きく加筆」と記されている箇所は、
おそらく下記と考えられる。「初出」では、「鏡の中の恍惚」の記述が2行ほどですが、
柏書房版では約2ページ半にわたる加筆改稿になっています。ちなみに、「蔵の中」は
角川文庫版『蔵の中・鬼火』(2018/7改版初版)という、現行本で読むことが可能となっており、そちらでは約3ページにわたる加筆改稿の分量に相当する。柏書房版:p.91下,15-16行, 角川文庫:p.123,16行 うろ覚えの曲を奏でてみたり〜 (この間、柏書房版では約2ページ半, 角川文庫版約3ページの加筆) 柏書房版:p.94上,13行, 角川文庫:p.126,17-18行 〜今度は古い遠眼鏡を持ち出して、 この間、柏書房版では約2ページ半, 角川文庫版約3ページの加筆となっていた箇所は、初出「蔵の中」では次の通り。 うろ覚えの曲を奏でてみたり、 それからどうかすると一日中鏡を覗いて、自分の美しさに恍惚として 時の経つのを忘れてゐる事もありますが、それにも飽きると、 今度は古い遠眼鏡を持ち出して、 初出では2行程度の文章だった箇所に対して、2,3ページ分の加筆を行ったうえで、前後を繋げるという改稿作業を、横溝正史は行っていたのには驚かされた。 今回、初出版「蔵の中」と柏書房版/角川文庫版を読み比べてみて、 「初出から大きく加筆」の他にも、細かな改稿(加筆)は多々あることがわかりました。 横溝正史の改稿癖が、昭和10年「蔵の中」刊行時に、すでにあったことに気づかされた次第。もっと以前の作品にも、改稿があるかもしれませんが…。 関連ページ: 横溝考古学・事始め (90):三つの「蔵の中」を読む -宇野浩二・江戸川乱歩・横溝正史- |
| 横溝正史に関する情報をご存知の方、 ぜひお知らせください。 |
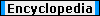 横溝ペディアへ |
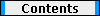 考古学事始めへ |
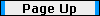 ページの先頭へ |