 『激動、昭和史の墓』 合田一道, 寿郎社, 2024/9/30, 本体2300円+税 | |
内容項目は次の通り。
| |
|
帯には、次の惹句がある。 鎮魂と記憶継承の〈旅〉へ 昭和九年生まれのノンフィクション作家が 時代を象徴する人や事件の跡をめぐる墓碑巡礼の記録  浜田知明「中絶長編『模造殺人事件』の消息」(『横溝正史研究5』戎光祥出版,2013/3)に、次の記載がある。
浜田知明「中絶長編『模造殺人事件』の消息」(『横溝正史研究5』戎光祥出版,2013/3)に、次の記載がある。昭和電工事件、下山事件が作中にそのまま織り込まれているのも珍しく、正史は『八つ墓村』で津山三十人殺し、『悪魔が来りて笛を吹く』で帝銀事件を取り込んではいるものの、いずれも設定を借りただけで、時期、場所などを変えており、作品の根幹を成す創作事件の遠因あるいは近因として、その導入部に用いているにすぎない。それが『模造殺人事件』では下山事件が作中世界でも実際にあったこととして、それを受ける形で物語が展開していく(似た例としては、「花園の悪魔」とメッカ殺人事件がある)。 「第15墓 津山三十人殺し」 この事件は長くタブー視されたままだったが、戦時中、岡山に疎開していた作家の横溝正史が事件の話を聞き、それをモデルに書いた小説『八つ墓村』によって広く知られるようになった。と、本文に言及がある →『八つ墓村』の田治見要蔵の32人殺しとして、取り込まれた。 「第35墓 下山事件」→『悪魔が来りて笛を吹く』の天銀堂事件 「第68墓 帝銀事件」→『模造殺人事件』の下山事件 こちらの二項目には横溝正史作品への言及はないものの、それぞれ『悪魔が来りて笛を吹く』『模造殺人事件』の作品背景を知るうえで、参考となる。 「第15墓 津山三十人殺し」の項で、「『八つ墓村』のモチーフに」「それをモデルに書いた小説『八つ墓村』」と記されているが、実情は異なる。横溝正史は「八つ墓村」執筆の意図を自身のエッセイ「思いつくまま」で、「八つ墓村」は坂口安吾「不連続殺人事件」に挑戦した旨を、語っている。 ハッキリいっておくが、私の「八つ墓村」の構想の最初のヒントは「不連続」である。但しいくらなんでも完成された「不連続」から、思いつきを頂戴しようとは思はなかったろう。あの小説がはじまったころ、わたしはまだ岡山県の農村にいて、評判はききながらも、雑誌が容易に手に入らなかつた。すると、それをきいて同じ岡山に疎開していた阿知波五郎氏が、第三回までひとまとめにして送ってくれたのだが、私はその三回で作者の意図を見破つたのである。これは「ABC殺人事件」の複数化であると。そう気がついたとき、私はなんともいへぬ戦慄と羨望を禁じえなかつた。それというのが、当時私は農村を舞台にして、そこに起こるいろんな葛藤を織込みながら、出来るだけたくさん人殺しのある小説を書いてみたいと考えていたのだが、それには一貫した動機を考へるのがむづかしかった。「ABC殺人事件」を複数化すれば、それが容易に出来るのである。私は「不連続」がうらやましくて耐えられなかつた(略) 「不連続」第四回の掲載誌は、ついに手に入らなかったが、(これが入手出来ていたら、私は金田一耕助に命じて作者の挑戦に応じさせていたのだが)そのあとは東京から武田武彦君が送ってくれた。そして、これはいよいよ最初、私のにらんでいたとおりだとハッキリしたころには、私の頭にだいたい「八つ墓村」の構想はまとまっていたのである。だから、「八つ墓」は「不連続」に挑戦したものといってもよい(略) また、「「八つ墓村」考 III」(『真説 金田一耕助』毎日新聞社1977/12,『横溝正史エッセイコレクション3』2022/6収録)で、津山事件を『八つ墓村』の書き出しに使用した旨を語っている。 当時の「新青年」は純粋の探偵雑誌とはいいにくく、むしろ大衆娯楽雑誌の傾向が強かったので、私も本格探偵小説の骨格はくずしたくはないが、ひとつスケールの大きな伝奇小説を書いてみようと思い立ち、それには津山事件はかっこうの書き出しになると気がついたからである。 以上のことからも、田治見要蔵の32人殺しは「八つ墓村」のメインストーリではなく、あくまでも小説の書き出しに設定を借用したに過ぎないことがわかる。つまり横溝正史は、現行角川文庫『八つ墓村』500ページ弱の本文のうち、最初のp.14-16(実質1ページ強に相当)で、次のように書いているだけである。  それは春のおそい山村では、まだ炬燵のいる四月下旬のある夜のことだった。
それは春のおそい山村では、まだ炬燵のいる四月下旬のある夜のことだった。村の人たちは突然、時ならぬ銃声と、ただならぬ悲鳴に眠りをさまされた。銃声は一発にとどまらず、間をおいて二発、三発とつづいた。悲鳴、叫声、救いを求める声はしだいに大きくなってきた。何事が起こったのかと表へ飛び出した人々は、そこに世にも異様な風体をした男を見た。 その男は詰襟の洋服を着て、脚に脚絆をまき草鞋をはいて、白鉢巻きをしていた。そしてその鉢巻きには点けっぱなしにした棒型の懐中電燈二本、角のように結ぴつけ、胸にはこれまた点けっぱなしにしたナショナル懐中電燈を、まるで丑の刻参りの鏡のようにぶらさげ、洋服のうえから締めた兵児帯には、日本刀をぶちこみ、片手に猟銃をかかえていた。村の人々はそれを見ると、だれでも腰を抜かさずにはいられなかった。いや腰を抜かさぬまでも、そのまえに男のかかえた猟銃が火をふいて、ひとたまりもなくその場に撃ち倒されてしまった。 これが要蔵だった。 かれはまず、そういう風体で、一刀のもとに妻のおきさを斬って捨て、そのまま狂気のように家を飛ぴ出したらしい。さすがに二人の伯母や子どもたちには手をつけなかったが、 その代わり、罪もない村の人たちを、当たるを幸いと、あるいは斬り捨て、あるいは猟銃で狙撃して回った。 後で調べてわかったところによると、ある家は表をたたいて訪れる声に、何気なく主人が、大戸をひらいたところをいきなり外からズドンと狙撃された。また、ある家では新婚の若夫婦の寝入りばなを、雨戸を一寸ほどこじあけて、そこから突っ込んだ銃ロで、まず花婿を撃ち殺し、物音に驚いてとび起きた花嫁が壁際まで逃げていって、助けてくれと手を合わせているところを、ズドンと一発やったらしい。手を合わせたまま死んでいる若い嫁の姿勢が、駆けつけてきた係官の涙をしぼった。しかも、この花嫁のごときは、つい半月ほどまえ、十里ほど向こうの村から嫁入ってきたばかりで、要蔵とは縁も由縁もない女であった。 こうして要蔵は一晩村じゅうを暴れまわったあげく、夜明けとともに山へ逃げこみ、ようやくにして恐怖の一夜は明けたのである。 翌日、急報によって近くの町々村々から、おびただしい警官や新聞記者が押し寄せてきたときには、八つ墓村は血みどろになっていた。あちらにもこちらにも血にまみれた死体がころがっていた。どの家からも瀕死のうめき声が洩れた。まだ死にきれないで助けを呼んでいるものもあった。 そのとき、要蔵によって重軽傷をおわされたものは数知れなかったが、即死したものは三十二人、実に酸鼻を極めた事件で、世界犯罪史上類例がないといわれている。 津山事件をモデル(=メインストーリ)にした作品としては、松本清張『ミステリーの系譜』の「闇に駆ける猟銃」、西村望『丑三つの村』(1983年映画化)などがある。これらの他にもあるようですが、当方未読ゆえ割愛します。  『東西ミステリーベスト100』(文春文庫,1986) <日本篇>「44位:八つ墓村」の項に、次の記述がある。
『東西ミステリーベスト100』(文春文庫,1986) <日本篇>「44位:八つ墓村」の項に、次の記述がある。その面白さはなんといっても後半の大洞窟迷路の冒険にある。 "猿の腰掛" "天狗の鼻" "木霊の辻"と呼ばれる洞窟内部、無数の枝迷路、 屍蝋と化した鎧武者、三千両の黄金……要するに日本的でロマンティックな 一大冒険伝奇スリラーなのであり、謎解きではなく、その味わいを 楽しむべき作品なのである。 私の『八つ墓村』への思いを、代弁しているような気がしています。 金田一耕助自ら「私は最初から犯人を知っていたのですよ。…(以下略)」と 語っているのですから(^^;)、犯人探しよりも超娯楽大作=エンターテインメント作品として『八つ墓村』を読む楽しみを発見できると考えます。あまり指摘されていないように思うのですが、『八つ墓村』には、幾重にも紡がれたラブストーリーが描かれているとも思います。どのようなラブストーリーが描かれているかは、ぜひ『八つ墓村』を読んで確認してみてください。 この刊本、『激動、昭和史の墓』の内容から大きく脱線してしまいました。申し訳ございません(^^;)。 | |
|
さて、次回の「ほぼ週刊・本棚から横溝正史」は…。 キーワードは「???」です。お楽しみに! |
|
横溝正史関連書籍をご存じの方、 耳寄りな情報をお待ちしております。 |
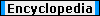 横溝ペディアへ |
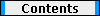 本棚からへ |
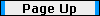 ページの先頭へ |