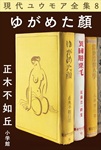 2025年6月27日付で、「現代ユウモア全集」第8巻『ゆがめた顏』(正木不如丘, [現代ユウモア全集刊行会]=現・小学館)電子版が配信開始された。文芸情報サイト「小説丸」の「現代ユウモア全集」特設サイトに、「現代ユウモア全集」の概説がある。
2025年6月27日付で、「現代ユウモア全集」第8巻『ゆがめた顏』(正木不如丘, [現代ユウモア全集刊行会]=現・小学館)電子版が配信開始された。文芸情報サイト「小説丸」の「現代ユウモア全集」特設サイトに、「現代ユウモア全集」の概説がある。昭和初期の1928年(昭和3年)に創刊された『現代ユウモア全集』は、当時大ヒットを記録。「ユーモア小説」が大衆文学の一ジャンルとして認知されていく初期の過程で、大変重要な役割を果たしました。 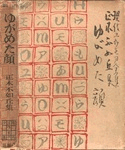 同サイトの『ゆがめた顔』の項では、正木不如丘の医師としての顔と合わせ、作家としての顔が紹介されている。
同サイトの『ゆがめた顔』の項では、正木不如丘の医師としての顔と合わせ、作家としての顔が紹介されている。正木不如丘は、医者兼作家。竹久夢二、堀辰雄、横溝正史らが入院した、日本初の高原サナトリウム=富士見高原療養所の初代院長を勤めた人物で、文筆もこなし、大正末から昭和前半にかけて、文芸誌から大衆娯楽誌、大手新聞まで様々な媒体に作品を発表、「第二の漱石」と囁かれたことさえあった。さらに、徳冨蘆花の主治医を務め、最期も看取った。  『横溝正史旧蔵資料 世田谷文学館資料目録1』(新保博久監修, 世田谷文学館, 2004/3)をチェックしてみたが、『現代大衆文学全集』(平凡社, 1927)、『大衆文学大系』(講談社, 1972)、『正木不如丘作品集』(正木不如丘作品集刊行会, 1967)など、正木不如丘作品の刊本所蔵に関する記載を見つけることができず。エッセイ「不如丘と不木」で、正木不如丘作品集の内容見本について記されているので、てっきり蔵書があると想像していたのですが…。見落としがあるかも…。それにしてもハテ?
『横溝正史旧蔵資料 世田谷文学館資料目録1』(新保博久監修, 世田谷文学館, 2004/3)をチェックしてみたが、『現代大衆文学全集』(平凡社, 1927)、『大衆文学大系』(講談社, 1972)、『正木不如丘作品集』(正木不如丘作品集刊行会, 1967)など、正木不如丘作品の刊本所蔵に関する記載を見つけることができず。エッセイ「不如丘と不木」で、正木不如丘作品集の内容見本について記されているので、てっきり蔵書があると想像していたのですが…。見落としがあるかも…。それにしてもハテ?正木不如丘の現行本としては、論創社『正木不如丘探偵小説選I』(2012/10)『正木不如丘探偵小説選II』(2012/11)があるくらいだったので、「現代ユウモア全集」の電子書籍としての復刊は、正木不如丘作品を周知するうえでも有り難い。現状、青空文庫への作品登録も少なく、論創ミステリ叢書以外に現行本がない状況を、何とか打開できないものだろうか。 | ||
| ||
|
荒川じんぺい「高原のサナトリウムに足跡を残した著名人たち」(結核予防会機関誌「複十字」No.351(2013/7) TBアーカイヴ)に、富士見高原療養所で療養された著名人に関する記述がある。文士関連では、藤沢桓夫、横溝正史、竹久夢二、堀辰雄らが紹介されている。横溝正史について、次のように記されている。 横溝正史は,昭和8年に入所し,一度退所したものの,翌年には,諏訪湖畔にある不如丘の屋敷の離れに家族共々住み,その後町内に移転し療養しながら小説を書いた。 横溝正史は、自身のエッセイで何度も正木不如丘の名前を記している。発表順に整理してみて気づいたのだが、医師としての正木不如丘がほとんどで、正木不如丘作品に触れた個所を見つけることはできなかった。見落としなどあるかと思いますが…。このほかにも、横溝正史が正木不如丘について記したものがあれば、ご教示ください。 「大阪の友人 藤沢桓夫君」新大阪新聞, 1952/1/27 昭和八年の春、私は大喀血をして、しばらく自宅で静養したのち、正木不如丘先生の富士見の療養所に入院した。 七月の暑いさかりのことである。白樺といかにも不如丘先生らしい風流な名のついた病棟の一室におさまって、何しろ汽車でつかれていたので、そのままごろりとベッドに横三なっていると、しばらくして、日光浴用の広いベランダづたいに、カタカタと下駄の音をさせ、窓から顔を出した白面の偉丈夫があった。明治時代の壮士のように肩をいからせて、 「ぼく、藤沢桓夫です」  横溝正史の短編「詰将棋」収録の光文社文庫傑作ミステリー集『将棋推理 迷宮の対局』(山前譲編, 2018/1)の巻末解説に、「大阪の友人 藤沢桓夫君」でも記されていますが、藤沢桓夫と横溝正史の関係に関する興味深い記述がある。
横溝正史の短編「詰将棋」収録の光文社文庫傑作ミステリー集『将棋推理 迷宮の対局』(山前譲編, 2018/1)の巻末解説に、「大阪の友人 藤沢桓夫君」でも記されていますが、藤沢桓夫と横溝正史の関係に関する興味深い記述がある。1934年、結核を患って療養した信州の富士見高原療養所に、先に入所していたのが藤沢桓夫だった。 横溝正史は大阪薬専に学んだが、そこで修身を教えていたのが藤沢桓夫の父だった。 藤沢桓夫は、『横溝正史追憶集』(1982/12)収録の「名探偵を生んだ人」において、さらに詳しく横溝正史の思い出を語っている。 「途切れ途切れの記」7 喀血で狼狽のこと 『横溝正史全集9』月報第7号, 1970/7  博文館を退いた翌八年の五月七日、私はとつぜん大喀血をやらかした。(略)
博文館を退いた翌八年の五月七日、私はとつぜん大喀血をやらかした。(略)ところがアニハカランヤである。富士見の療養所で正木不如丘先生に一喝されるに及んで、私ははじめてじぶんの病気の、なみなみならぬものであることを、ハッキリ認識したのだから、まことにノンキなことであった。(略) すると昭和九年の春の終わりごろ、とうとうたまりかねたのか、水谷準君が森下先生や大下宇陀児氏ほか先輩友人を代表してやってきて、私に宣告をくだした。 むこう一年絶対に筆をとらぬこと。女房子供をつれてどこかへ転地すること。以上二ヵ条の条件をのむならばむこう一年生活を保証しよう。(略) 私はひとのお世話になることが、あまり苦にならない性分だとみえて、有難くこのご好意をお受けすることにして、昭和九年七月末に信州上諏訪へ転地していった。上諏訪という土地がえらばれたのは、正木不如丘先生の御本宅がそこにあったからである。  「続・途切れ途切れの記」2 上諏訪時代のこと
「続・途切れ途切れの記」2 上諏訪時代のこと『定本人形佐七捕物帳全集 第2巻』月報第2号, 1971/4 昭和九年七月末、私は胸の疾患の療養のため、家内とふたりの子どもをつれて信州上諏訪へ転地した。(略) このとき療養地として上諏訪がえらばれたのは、その前年富士見の高原療養所で三ヵ月ほどお世話になったことがあり、そこでもういちど富士見へいってみたらどうかと思い、ひとを介して所長の正木不如丘先生にご相談申し上げたのである。 当時正木不如丘先生は上諏訪に本宅をもっておられたが、 一週間に二回、赤坂の前田外科へ出張していられた。そこへ友人に相談にいってもらったのだが、不如丘先生のご意見では富士見はたいへんである。冬場などとても住んでいられるものではない。それより上諏訪へいらっしゃい。上諏訪ならよい病院もあるから、紹介してあげようとのことなので、さっそくそれにきめ、おなじ友人に上諏訪へ借家さがしにいってもらったが、当時のことだから借家などいくらでもあった。(略) 正木不如丘先生のご忠告にしたがって、上諏訪の気候風土になれるまで、ベッド生活をつづけていた私も、秋風が立ちはじめると同時に、じぷんでじぷんを訓練しはじめた。(略) 「鬼火」についてもおなじことがいえるので、正木不如丘先生から上諏訪はどうかとすすめられると、矢も楯もたまらずそこへいきたくなったのは、そこに湖水があるからである。私はまえにいちど上諏訪へ旅行したことがあり、諏訪の湖をしっていた。  「続・途切れ途切れの記」4 神沢太郎先生のこと
「続・途切れ途切れの記」4 神沢太郎先生のこと『定本人形佐七捕物帳全集 第4巻』月報第4号, 1971/6 正木不如丘先生は上諏訪に本宅をお持ちとはいうものの、お忙しい体だから、諏訪に患者をもつというわけにはいかなかった。そこで茅野病院という上諏訪きっての大きな病院の、院長先生に私のことを托された。 この茅野先生の甥ごさんで、おなじ病院に勤務していられた神沢太郎先生という人物が、主として私の面倒をみてくださることになった。 「不如丘と不木」 『医療芸術』1973/2 去年の暮れ古い手紙類を整理していると、つぎのような封書がでてきた。消印をみると41.12. 7とはっきり出ている。差出人は正木良一、すなわち正木不如氏先生のご長兄でいらっしゃる。なかみは正木不如丘作品集刊行にあたっての内容見本で、その「刊行のことば」として木々高太郎がつぎのごとく書いている。 「正木先生は当時の帝国大学の医学部を出て銀時計をもらった。青山内科に入り、後に仏蘭西に留学して帰って、当時新設の慶応大学医学部の内科の助教授になった。あとで富士見高原療養所長となった。恐らく先生には最初の学生が僕のクラスであったと思う。(中略)ところが何よりも学生達を驚かしたのは、忽ち先生は正木不如丘というペンネームで、随筆や小説を書き出したことで、(中略)今から考えると不如丘の得た当時のマスコミの人気は、恐らく日本の文壇ではまれであったろうと思われる。(後略)」 万事世事にうとい私は、木々高太郎のこの一文を読んで、はじめて正木先生と高太郎、高太郎の弟分みたいな椿八郎との関係をハッキリ知ったのだが、(略)大正の末期に出版された「とかげの尾」「木賊の秋」などは文字どおり当時のペストセラーであった。 先にも記したが、このエッセイに正木不如丘作品集の内容見本関する記述はあるものの、『横溝正史旧蔵資料 世田谷文学館資料目録1』(新保博久監修, 世田谷文学館, 2004/3)をチェックした限りではあるが、正木不如丘作品の刊本所蔵に関する記載は見当たらない。 その正木先生の名がとくに強く印象にのこったのは、大正十五年の「新青年」の新年号に発表された「赤いレッテル」という小説である。ずいぷん昔のことなので小説の内容は忘れているが、赤いレッテルというのは薬局瓶に貼られるレッテルのことである。ところがその小説に出てくる瓶の内容は塩化モルヒネであった。塩化モルヒネは毒薬であるから、当然その瓶に貼られるレッテルは青でなければならない。それを先生まちがって、つい劇薬に貼られる赤いレッテルとやられたからたまらない。なにがさて人気絶項の正木先生、文壇方面の風当りも強かったに違いない、早速なにかの維誌で痛烈にヤジられた。 ところで、なぜ、ここに先生のわずかなミスを取りあげたかというと、じつはこのヤジ記事を読んでショックを受けたのは、当の先生よりも私だったのではないかと思うからである。「新青年」のおなじその号に拙作「広告人形」というのが出ているくらいだから、私も 「赤いレッテル」を読んでいたのである。それでいながら某誌のヤジ記事を読むまでこのミスに気がつかなかった。しかも、おお、神よ、 私は薬剤師で、当時神戸で薬局を経営していたのである。これでは薬剤師失格であると、ヘボ薬剤師先生、いっぺんに自信喪失してしまったのだからダラシがない。その年の六月私は上京して博文館へ入社すると同時に、神戸の薬局を弊履のごとく捨てているが、そのときの薬剤師としての自信喪失がいくらかでも原因しているとすると、正木先生のミス、横溝正史をして薬剤師より雑誌記者にヘンシンせしめたというべきか、おかげで命拾いをしたお得意様があったかもしれぬ。 横溝正史は大阪薬専(現在の大阪大学薬学部)卒で、薬剤師免許を有し、当時春秋堂薬局という名の薬局を経営していた現役の薬剤師だったため、自身の不甲斐なさを「ヘボ薬剤師先生」と称して嘆いているものと推察する。医師・正木不如丘と薬剤師・横溝正史に関する逸話が、この他にも実はまだあるように思うのは私だけだろうか。 その私が昭和八年大喀血をやらかして、富士見高原療養所でお堆話になるはめになったのだから、これもなにかの因緑だろう。 療養所では三ヵ月しかお世話にならなかったが、その翌年先生のおすすめにしたがって、先生のご本宅のある上諏訪へ、私は一家をあげて転地している。そして十四年の暮れ東京へ引き揚げてくるまで、足かけ六年まる五年と五ヵ月上諏訪で療養生活を送った。先生は高原療養所のほかに、東京にも診療所をもつというご多忙さだったので、お膝下の上諏訪では患者をもっていられなかった。したがって私の診療などもご昵懇の先生に一任されたが、先生がおなじ上諏訪にいられるということが、私にとっていかに心強かったかはいうまでもない。 病いに小康をえて散歩ができるようになると、私はちょくちょく湖畔にある先生のお宅を訪問した。小柄ではあったが、精悍で、ファイ卜満々という正木先生ではあったが、なぜか当時は筆を断っていられたようである。そのことについてお訊ねしたことがあるが、先生は笑って答えられなかった。富士見の療養所にはずいぷん多くの文士、画家、ジャーナリス卜がお世話になっているから、先生としてはいちいち文学談などたたかわしてはいられなかったのだろうし、それより医家としての立場を堅持していられるのであろうと思って、私も二度と文学のことにはふれなかった。 おそらく唯一と思われるが、横溝正史が作家・正木不如丘について語った個所ではなかろうか。 上諏訪へ転地したとき先生がわれわれ夫婦に最初に与えた注意は、なまの鮒を食べないようにとのことであった。諏訪の鮒は肝臓ジス卜マをもっているんでね、じつはぽくもそれにやられているんだと苦笑していられたが、昭和三十八年逝去された先生のご病気も、それであったとうかがっている。先生のご冥福を祈るや切である。 「現代日本文学大事典」によると、正木不如丘先生が帝大の医学部を出られたのが大正二年、その翌年小酒井不木先生がおなじ医学部を出ていられるから、小酒井先生のほうが一年後輩ということになるが、私がお眼にかかったのは小酒井先生のほうがさきだった。 小酒井不木も、正木不如丘と同様に医師でもあり作家でもあった。小酒井不木のほうは、横溝正史とも作家として近しい関係だった。残念ながら、正木不如丘と横溝正史とは作家としての関係ではなく、医師と患者の関係を越えなかったようである。当方、鮒などの淡水魚をナマで食したことはないと思うが、正木不如丘が肝吸虫による病で、短命に終わったことは残念でならない。 「山荘愚談」 『推理文学』1974/12 昭和八年私は富士見の高原療養所で三ヵ月お世話になったことがあるが、そのとき所長の正木不如丘先生からこういうご注意をうけた。富士見と東京では気圧がそうとう違っている。だから移動した当座一週間くらいは安静にしていてほしいと。ことしほど身にしみて不如丘先生のこのご忠告を思い出したことはない。私はまるで酸欠病にかかった金魚みたいにアップアップしながら、それに寒くもあるので毎日電気コタツを最強にして、昼も夜も、寝床の中でウツラウツラと寝て暮らした。 高度順応といったところでしょうか。 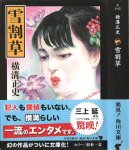 角川文庫『雪割草』巻末解説(山口直孝), 2021/4
角川文庫『雪割草』巻末解説(山口直孝), 2021/4『新潟毎日新聞』は、 文芸関係にカを入れた紙面作りに特徴があり、地元の文化人を登用する以外に中央で活躍する作家にも寄稿させている。連裁小説では探偵小説の掲載にも意欲的で、甲賀三郎『顔のない顔』(1938年6月26日~12月25日、全180回。挿毅/伊勢良夫。『蟇屋敷の殺人』の初出)や小栗虫太郎『女人果』(1939年1月1日~8月8日、全219回。挿絵/中島喜美)を提供している。また、それらに先立ち、1937(昭和12)年5月8日からは、正木不如丘『処女地帯』が連裁されていた。連載予告では「本社ではかねて新聞小説の向上に心掛け新機軸を開かうと種々考慮中でありましたが、今回正木不如丘博士をわづらはして8日付昼刊より"処女地帯"を連載することになりました。(略)/本社が今回、新聞小説の選定態度を急角度に変更し、特に正木博士の登場を煩はした理由は、旧来の囚はれた連載ものの型を破つて、新聞小説に一新生面を開拓しようとする野心の大胆な表現に外なりません。」(5月7日)と謳われている。 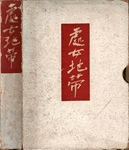 角川文庫『雪割草』の巻末解説にも、正木不如丘に関する記述があった。『新潟毎日新聞』において、1937:正木不如丘『処女地帯』 → 1938:甲賀三郎『顔のない顔』(『蟇屋敷の殺人』初出) → 1939:小栗虫太郎『女人果』 → 1940:下村悦夫『深夜の大陸』 → 1941:横溝正史『雪割草』 → 1942:鶴見祐輔『七つの海』と、正木不如丘から甲賀三郎・小栗虫太郎・下村悦夫らを経由して横溝正史へ、新聞連載小説のバトンがリレーされていたことになるようである。単なる医師と患者の関係だけではなく、作家としての関係も見え隠れしているように感じる。しかしながら、上記のエッセイに正木不如丘の名は出て来るものの、そのほとんどが医師としてのものであり、横溝正史は作家としての正木不如丘について多くを語っていない。
角川文庫『雪割草』の巻末解説にも、正木不如丘に関する記述があった。『新潟毎日新聞』において、1937:正木不如丘『処女地帯』 → 1938:甲賀三郎『顔のない顔』(『蟇屋敷の殺人』初出) → 1939:小栗虫太郎『女人果』 → 1940:下村悦夫『深夜の大陸』 → 1941:横溝正史『雪割草』 → 1942:鶴見祐輔『七つの海』と、正木不如丘から甲賀三郎・小栗虫太郎・下村悦夫らを経由して横溝正史へ、新聞連載小説のバトンがリレーされていたことになるようである。単なる医師と患者の関係だけではなく、作家としての関係も見え隠れしているように感じる。しかしながら、上記のエッセイに正木不如丘の名は出て来るものの、そのほとんどが医師としてのものであり、横溝正史は作家としての正木不如丘について多くを語っていない。横溝正史が過ごした、上諏訪・富士見をいつか訪れてみたいと思う次第。正木不如丘昨比を読むことで、富士見・上諏訪での療養時代の横溝正史界隈の状況もきっと見えてくると、考える次第である。  児平美和『正木不如丘文学への誘い』(研究叢書②, 万葉書房, 2005/9)という、正木不如丘文学のガイドブックが刊行されている。帯には、次の通り紹介されている。
児平美和『正木不如丘文学への誘い』(研究叢書②, 万葉書房, 2005/9)という、正木不如丘文学のガイドブックが刊行されている。帯には、次の通り紹介されている。正木不如丘を知っていますか? 大正から昭和にかけて結核医師でありながら、 作家としてもその才能を発揮した異色の文学者。 不如丘の全生涯をまとめた1冊です。 本文中で、『蜥蜴の尾』『木賊の秋』は「当時のベストセラーになった」(横溝正史評)と引用している、横溝正史「不如丘と不木」(『医療芸術』昭和48年2月号 日本医家芸術クラブ)は、「第二章 正木不如丘主要文献目録」の「回想録・人物紹介など」でも、リストアップされている。「第三章 正木不如丘作品年譜」「第五章 徒然~不如丘作品案内」を座右に、正木不如丘作品を読み進めていきたい。現行刊本は少ないものの、国立国会図書館デジタルコレクションで、相当数の正木不如丘作品を読むことができるのは、幸いである。  横溝正史は、「探偵小説と療養生活」というエッセイを、「結核療養雑誌」と銘打たれた『むつび』1946(昭和21)年8月創刊号に寄稿している(論創社『横溝正史探偵小説選III』論創ミステリ叢書37, 2008/12収録)。そこに興味深い記述がある。
横溝正史は、「探偵小説と療養生活」というエッセイを、「結核療養雑誌」と銘打たれた『むつび』1946(昭和21)年8月創刊号に寄稿している(論創社『横溝正史探偵小説選III』論創ミステリ叢書37, 2008/12収録)。そこに興味深い記述がある。私は探偵小説を作者と読者の智的協議の文学だと思っている。 (略) 諸君も、もし、優れた探偵小説をお読みになれば、自分でも一つ、面白い謎やトリックを考えてみようという野心を起すようになるだろう。そうなればしめたものだ。諸君の健康恢復は疑いなしである。 横溝正史は、自分の職業が探偵小説だったので、療養中は探偵小説と距離を置いた旨を記しているが、一般的には療養には探偵小説を奨めるとある。横溝正史カムバックの素地は、探偵小説にあったことは間違いないと考える次第。 |
| 正木不如丘と横溝正史に関してご存知の方、ぜひご一報ください。 |
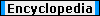 横溝ペディアへ |
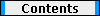 考古学事始めへ |
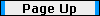 ページの先頭へ |

