|
創元推理倶楽部・秋田分科会編『定本 金田一耕助の世界』(2004/3)に私が寄稿した、 「エピソード3 - 大陸へ、南方へ -」(風間俊六名義)の、オリジナル原稿です。 横溝正史が記した金田一耕助事件記録では、昭和12年『本陣殺人事件』の次は、9年後の戦後へと舞台は移り、 昭和21年「百日紅の下にて」『獄門島』である。この9年間の空白を補完するため、横溝正史は作品中に語られざるエピソードを散りばめた。これらを年代順に集めると、この期間の金田一耕助の足跡を辿ることが可能となる(特記なき限り、角川文庫緑三〇四の刊本より引用)。 ■1. 探偵小説「雪国」 金田一耕助のすすめで、私がこれから記述しようとするこの恐ろしい物語は、昭和十×年×月×日、国境の長いトンネルを汽車が通り抜けたところから始まった。 そこはもう雪国である。事件の舞台となったこの雪国には湯−温泉という名で知られる湯治場があり、保養客を集めるのがこの辺りの村々のもっとも主ななりわいの道であった。 信号所に汽車が止まったのは、夜の八時ごろのことだった。夜の底が白くなった、と私は感じたのだけれど、今にして思えば、恐怖の前兆で髪の毛が白くなったのではないかという気がする。それほど私は恐ろしい経験をしてきたのだ。 私の前の席に坐っていた女が、つと立って窓を開けた。冷たい風が吹き込むので、もうそんな寒さかと外を見ると、雪の色は地獄のような闇に呑まれ、私はつめたい戦慄が背筋をつらぬいて走るのを禁じえなかった。 女は窓から乗り出して駅長を呼んだ。明りを下げてゆっくり近づいて来た男は、襟巻と毛皮の帽子で顔をすっかり隠していた。おお、それがこのまがまがしい事件の発端になろうとは、まだだれも気がついていなかったのである。 (和田誠「お楽しみは雪国だ 横溝正史」より引用) ※『本陣殺人事件』以後、金田一耕助が出征するまでの間に、「雪国」という事件があるようです。川端康成の「雪国」のプロットをそのまま利用して、横溝正史が探偵小説を書いたらという試みを、和田誠が「お楽しみは雪国だ 横溝正史」(『倫敦巴里』,話の特集,1977/8)で行っている。ユニークな試みなのですが、導入部のさわりで終わっているのが、実に悔やまれます。探偵小説「雪国」は、どのようなプロットだったのか。ヒロイン駒子は登場するのか。想像するのも楽しいですね。川端康成『雪国』は、1937(昭和12)年6月刊行。1935-1937年に断続的に発表したものを、補筆改稿された事実を基にすると、昭和十×年は『本陣』以前ともとれますが、ここでは、『本陣』以後金田一耕助出征前までの事件と仮定しました。 ■2. 運命の出会い -等々力大志- 金田一耕助と等々力警部は、ずいぶん古い馴染みである。昭和十二、三年ごろ、警部の持てあましている事件を、横からひょっこりとび出した耕助が、みごとに解いてみせたことがあった。(『悪魔が来りて笛を吹く』p.97) ※東京に探偵事務所開設後のエピソードと考えられる。横溝正史は、等々力警部関連の事件記録を数多く記しているが、等々力警部と金田一耕助の出会いとなった事件記録を記していない。というよりは、その時期を曖昧にしている。「暗闇の中の猫」p.143に「この二重殺人事件がきっかけとなって、等々力警部と知り合いとなり、(略)」とあり、『悪魔が来りて笛を吹く』p.97と齟齬をきたしている。これは弘法も筆の誤りで、「…事件がきっかけとなって、戦後等々力警部と再会し」たのでしょう。等々力警部との最終作『病院坂の首縊りの家』は、金田一耕助最後の事件と銘打ち、あまりにも有名な事件記録となった。『病院坂』以降に執筆予定だった事件記録で、等々力警部との出会いのエピソードを語る予定だったのかもしれない。『本陣』で磯川警部との出会いを描き、『悪霊島』では磯川警部の人生を語ったように。 ■3. 陸軍伍長 金田一耕助 金田一耕助が岡山県の農村の、旧本陣一家で起こったあの不思議な殺人事件のなぞを解いたのは、昭和十二年のことであり、当時かれは二十五、六歳の青年だった。その後かれはなにをしていたか。−なにもしなかったのである。日本のほかの青年と同じように、かれもまたこんどの戦争にかりたてられ、人生でいちばん大事な期問を空白で過ごしてきたのである。 最初の二年間かれは大陸にいた。それから南の島から島へと送られて、終戦のときにはニューギニアのウエワクにいた。 この一戦で部隊は全滅にひとしい打撃をうけて敗走した。その後、他の部隊と合流して、部隊の編成替えがあったが、そのとき、いっしょになったのが鬼頭千万太であった。鬼頭は、かれより四つ若かったが、かれもまた昭和十年に学校を出ると、すぐ大陸へ持っていかれ、耕助と同じようなコースをたどって、ニューギニアまでやってきたのであった。(『獄門島』p.14) ※大陸から南方へ転戦するにあたり、一度帰国したという仮定の基、井沢元彦が『GEN 源氏物語秘録』のなかで、金田一耕助に関する活動記録を補完している。 「(略)少し前まで、大陸の連隊にいた。ところが、連隊が今度別のところに配置換えになることになったので、とりあえず一度内地に引き上げてきたということさ。(略)」(p.234) 「装備だよ。これまで零下何十度の極寒に耐えられるはずの装備が全部没収され、新たに熱帯で使うようなものばっかり与えられた。あれはどう見ても南方へ行くとしか、考えられない」(p.236) 「(略)そこ(カリフォルニア)で少し探偵の真似事をして、皆に褒められたことがある(略)」(p.237) 「(略)だが、探偵をあまく見ちゃいけないよ」(p.241) 「陸軍伍長、金田一耕助であります」(p.242) (以上、角川文庫『GEN 源氏物語秘録』より抜粋) この会話の交わされた場所は、京都・金閣。金田一耕助は大阪八連隊に所属していたことになっている。 ■4. 探偵の見た戦争 ※太平洋戦争に従軍した金田一耕助。彼の見たものは、いったい何だったのだろうか。 昭和十八年以来そこには一度も戦闘はなかった。アメリカ軍はもう、そんじょそこらに残っている小部隊には眼もくれず、大きく飛躍していたのである。こうして敵の後方ふかく取り残された耕助たちは、友軍との連絡もなく、希望のない、暗澹たる日々を雑草とたたかってくらした。 そうしているうちに戦友は、熱病と栄養失調とで続々とたおれていった。補充のつかぬ前線では、ひとり死ねばひとり減る。 部隊はしだいに残り少なくなり、生き残った連中はいよいよ絶望感にむしばまれていった。軍服も軍靴ももうボロボロになっており、だれもかれも島の俊寛といったていたらくだった。 そこへ終戦が来たのである。(『獄門島』p.15) ニューギニアで死んだ、戦友の川地謙三に「佐伯一郎氏を訪ねて、この事件について談合し、謎を解いてくれたまえ」とことづけられる。(「百日紅の下にて」/『殺人鬼』p.238) 数年間の前線生活だ。耕助はいやというほど、人間の死ぬところを見てきた。爆死もあれば病死もあった。それらの死体を、つねに注意ぶかく見まもることを忘れなかった耕助は、死後硬直の状態について、一種の鋭い勘を持っていた。(『獄門島』p.100) そのうちに私が兵隊にとられたので、(風間俊六と)また縁が切れてしまった。そう、六、七年もあいませんでしたかねえ。(「黒猫亭事件」/『本陣殺人事件』p.360) ■5. 復員船 「(略)おれはもうだめだ。金田一君、おれの代わりに……おれの代わりに獄門島へ行ってくれ。……いつか渡した紹介状……金田一君、おれはいままで黙っていたが、ずっとまえから、きみがだれだか知っていた……本陣殺人事件……おれは新聞で読んでいた……(略)」 鬼頭千万太はそこまで言って、がっくり息が絶えてしまったのである。 臭い、煮えくりかえるような復員船の熱気の中で…… (『獄門島』p.28) 「ふむ。兵隊にとられるまでは東京に住んでいたが、かえってみたらきれいさっぱり焼けていた。だから、当分こうして島から島へと流れ歩くつもりさね」(『獄門島』p.29) ※初代探偵事務所は戦争により焼けてなくなったようだ。どこにあって、どんな様子だったかは、今をもって不明である。そして復員後、百日紅の下で戦友の川地謙三の頼みを果たした金田一耕助。 「あっ、ちょっと…あなたの名は…あなたのお名前は?」 「私の名前ですか、私の名は金田一耕助。とるに足らぬ男です」 蒼茫と暮れゆく廃墟の中の急坂を、金田一耕助は雑嚢をゆすぶり、ゆすぶり、急ぎ足に下っていった。瀬戸内海の一孤島、獄門島へ急ぐために−。(「百日紅の下にて」『/殺人鬼』p.270) ※このフレーズが好きな方も、多いのではないでしょうか。 (略)その島(獄門島)へ渡るまえにパトロンの久保銀造のところへ立ち寄った。ところがそこで、自分のことを小説に書いている人がある、ということをきいて大いに驚いた。自分もその小説を読んだ。そこで島へ立つまえに、雑誌社へ手紙を出して、作者の居所を訪ねておいたのだが、(略) (「黒猫亭事件」/『本陣殺人事件』p.284) 金田一耕助は思い出す。かれはここへ来るまえに、パトロンの久保銀造のところへ立ち寄ったが、そのとき銀造はつぎのようなことをいったのである。 「耕さん、あんたが獄門島へ行くのは、ただ戦友の死を伝えるためだけかな。それならばよいが。……もし、そのほかにあんたがなにか目的を持っているのなら、なにか心に、いだいていることがあるのなら、わしはあんたを、引き止めたいと思うよ。獄門島って耕さん、あそこはいやな島だよ。恐ろしい島だよ。耕さん、あんたはあそこへなにしにいくのかね」 金田一耕助を理解することもっとも深い銀造はそういって、気遣わしそうに、探るようにかれの顔色をうかがっていた。……(『獄門島』p.16) だれしも終戦をよろこばぬものはなかった。また、だれしも蛆虫のように死んでいくことに嫌悪を感じないものはなかった。しかし、鬼頭千万太ほど深刻に死を恐れる男はほかになかったのである。マラリアが再発するごとに、子供が闇におびえるように、かれは死のかげにおののいた。体も大きくがっしりとして、気性も強く、ほかのあらゆることに対しては、だれよりも勇敢だったこの男にしては、それはたしかに不自然だった。あまりにも強い、露骨なこの男の生への執着には、どこか不気味なところさえあった。それにもかかわらずこの男は死んだ。しかもあと五、六日で故国の土を踏めるという、復員船のなかで……。そして、そしていま金田一耕助は、かれの死を遺族のものに伝えようと、獄門島へ向かっているのである。(『獄門島』p.15-16) ※こうして『獄門島』の幕は、切って落とされた。 横溝正史の書いた金田一耕助事件記録に、断片的に散りばめられた語られざるエピソードをつなぎ合わせてみると、流れのあるサイドストーリが浮き彫りになることがわかります。横溝正史は金田一ものの作品を通じて、いくつものサイドストーリを透かしのごとく作品に忍ばせたことを窺い知ることができました。横溝正史は、作品の行間を利用して、サイドストーリを読者に提供していたのです。 ◆別執筆者による補完エピソード ◇昭和12年11月『本陣殺人事件』 ◆昭和1X年冬 和田誠「お楽しみは雪国だ」 (『倫敦巴里』,話の特集,1977/8) ◆昭和13年12月 藤村耕造「陪審法廷異聞 -消失した死体」 (『金田一耕助の新たな挑戦』,角川文庫,1997/9) ◆昭和15年秋 井沢元彦『GEN 源氏物語秘録』 (角川文庫,1998/10) ◇昭和21年9月「百日紅の下にて」 ◆昭和21年10月 姉小路祐「生きていた死者」 (『金田一耕助の新たな挑戦』,角川文庫,1997/9) ◇昭和21年10月『獄門島』 |
| 金田一耕助について調査中です。 知りたいテーマがありましたら、ぜひご一報ください。 |
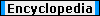 横溝ペディアへ |
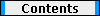 ターヘルアナトミアへ |
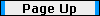 ページの先頭へ |